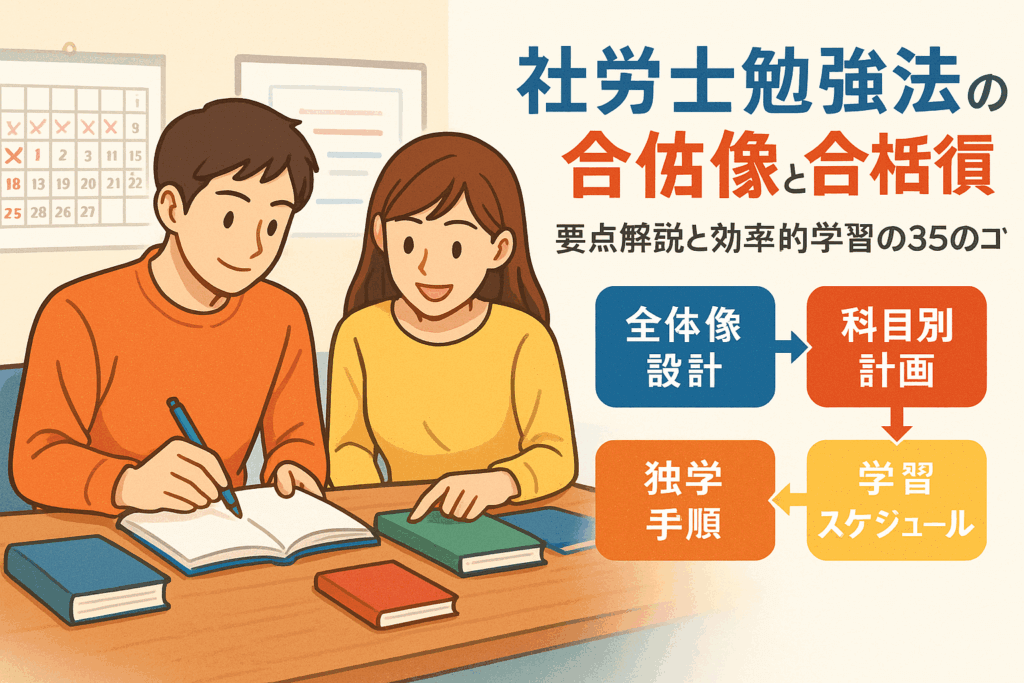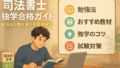「社労士試験の合格率は、直近【6.4%】という狭き門。その一方で、受験者の約【7割】が独学と通信講座を選んでいます。しかし、『自分に本当に合う勉強法はどれ?』『効率よく合格ラインへ到達できるか不安…』と悩んでいませんか?
実際、合格者の平均勉強時間は【800~1,000時間】とされていますが、多忙な社会人や主婦でも半年~1年で合格を実現するケースも珍しくありません。ポイントは、自分の生活リズムや得意・不得意に合わせて学習計画と教材を最適化することにあります。
本記事では、2025年対応の最新動向を徹底調査。科目別の出題傾向分析、独学・通信・通学講座のメリット比較、実際の勉強スケジュールや「挫折しないコツ」まで、豊富なデータと体験例をもとに解説します。
「何から始めるべき?」「忙しくても続けられる?」と迷った方も、読み進めれば安心して一歩を踏み出せる具体策が必ず見つかります。続きで、今すぐ役立つ最新攻略法を手にしてください。
社労士の勉強法とは全体像と2025年最新動向解説
社会保険労務士試験の対策は年々進化しており、2025年は独学・通信講座・通学講座など多様な選択肢が広がっています。社労士は「短期集中型」から「長期計画型」まで学習スタイルもさまざまです。現在は、効率的な勉強法やノート術、デジタル学習ツールの活用、自分に合う参考書・テキスト選びの重要性が高まっています。数ある勉強法のなかでも、合格者が取り入れている方法は共通しており、スケジュール・教材・アウトプットのバランスが鍵となっています。
独学・通信講座・通学講座の使い分けと特徴比較 – 独学と予備校・通信講座の具体的メリット・デメリットを最新情報で掘り下げる
学習方法には独学・通信・通学それぞれ特徴があり、下記のように比較できます。
| 学習方法 | 主な特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 独学 | 自由度が高い、自分のペースで進められる | 費用が安く、好きなテキストやアプリが使える 独学でも合格体験記は多数あり、自力突破も可能 |
計画や理解不足で挫折しやすい 質問・相談の機会が少ない |
| 通信講座 | 教材やサポートが充実、オンライン学習が主流 | 分かりやすい解説や動画、質問対応が魅力 自宅で予備校並みの体験ができる |
費用が独学より高い、モチベーション管理が自己責任 |
| 通学講座 | 講師から直接指導、仲間と切磋琢磨できる | 仲間や講師の存在で継続しやすい 対面型で質問しやすい |
費用が高額、通学時間が必要 スケジュールが固定 |
このように、自分に合ったスタイルを選ぶことで学習効率が大きく変わります。最近はスマートフォン用の「社労士勉強アプリ」や「ノートアプリ」も人気で、テキスト・問題集を組み合わせる独学+デジタル併用例も多いです。
合格者に共通する学習習慣と挫折しやすいパターンを徹底分析 – 合格者の勉強時間管理・学習習慣と、挫折の原因を具体例で示し対策を提案
社労士試験の合格者に共通する学習習慣は以下の通りです。
-
毎日一定の勉強時間を確保する習慣
-
アウトプット中心の学習(過去問演習・問題集の反復)
-
自作ノートやアプリの活用で復習効率を高める
-
計画的なスケジューリングと進捗管理
-
勉強内容を見える化し、達成感を得る工夫
よくある挫折パターンは「長期計画が立てられず、途中でモチベーションが切れる」「一人で抱え込んでしまい疑問点が解消できない」「ただテキストを読むだけで理解が浅い」などです。対策としては、
-
スケジュール管理をカレンダーやアプリで“見える化”する
-
毎週小目標を作る
-
SNSや勉強サイトで情報交換し孤独を解消する
-
苦手分野は重点的に繰り返し対策する
これらを意識することで、効率よく学習を進めやすくなります。テキストやアプリの比較、合格者の体験談も参考になり、独学でも継続的な成長が期待できます。
科目別出題傾向分析と効率的な学習計画の立て方
社労士試験で高得点を狙うには、科目ごとの出題傾向を把握し、効率の良い学習計画を立てることが重要です。自分の得意・不得意分野を明確にし、暗記系や思考力が求められる問題をバランスよく組み合わせて学習を進めましょう。さらに、過去問や模擬試験を活用することで本番の出題傾向や難易度にも慣れることができます。各科目の特性を理解し、次のポイントを意識して取り組むことが合格への近道です。
労働関連科目の攻略ポイント詳細 – 労働基準法・労災保険など労働系科目の理解度アップ法と要点整理
労働基準法や労災保険は出題率が高く、正確な条文理解が求められます。特に、判例や改正点に注目し、毎年変化する部分を重点的に抑えましょう。簡潔なまとめノートの作成や、分かりやすい表で規定・数値を整理すると知識の整理に役立ちます。
労働科目の学習ポイント
-
改正点のチェック
-
判例の整理
-
択一・選択式対策に過去問を活用
自分専用のサブノートを作ることで、繰り返しの復習や記憶定着が促進されます。おすすめの勉強方法としては、1日1テーマを決めて演習問題と条文の読み込みを繰り返すことです。
社会保険系科目の学習ステップと注意点 – 健康保険・年金制度・雇用保険の出題傾向と学習コツを具体的に解説
社会保険系は覚える範囲が広いため、効率よくポイントを押さえる必要があります。年金制度や健康保険は改正が多く、特に数字や給付内容の違いに注意しましょう。
ステップごとの学習法
- 体系図で全体像を掴む
- 過去3年分の頻出論点を抽出
- 比較表を使いながら各制度の違いを整理
重要な部分は強調マーカーや付箋で可視化し、隙間時間にはスマホの勉強アプリも取り入れると学習効率がアップします。複雑な制度や例外規定は、まとめノートに整理しておくと直前対策でも役立ちます。
一般常識、白書の効果的勉強法 – 一般常識や白書問題で高得点を取るためのポイントと教材選択ガイド
一般常識や白書問題は他の科目と比べて範囲が広いですが、基礎固めと最新トピックスのインプットが必要です。最新の白書対策本や無料の情報サイトを活用し、直前期は統計や用語を暗記カードでチェックしましょう。
| 推奨教材 | 特徴 |
|---|---|
| 一般常識対策テキスト | 厳選トピックに絞った要点整理 |
| 白書まとめアプリ | 例年重要ポイントを一問一答形式で学習 |
| 白書PDF資料 | 時事・統計のデータ確認に便利 |
過去問で頻出分野を分析し、時事問題は普段からニュースや公的資料にも目を通すことが重要です。
過去問活用術と模擬試験の効果的な回し方 – 過去問を使った演習計画や模試活用法の具体的指針
過去問は知識の定着や本試験レベルの把握だけでなく、苦手分野のあぶり出しにも最適です。年度・科目ごとに複数回転し、解説まで丁寧に読み込むことが大切です。模擬試験は本番と同じ時間配分で実施し、ペース配分やマークシートの練習も忘れずに行いましょう。
過去問・模試活用ポイント
-
3~5年分を一巡後、間違えた問題だけを重点的に復習
-
模試の成績表で弱点科目を洗い出す
-
直前期は総合問題を数回実施し本番形式に慣れる
着実な演習サイクルを習慣化して、実力アップと合格への自信につなげていきましょう。
独学で社労士を合格するための詳細勉強スケジュールと時間管理術
半年・1年・2年など期間別成功プランの具体例 – 多忙でも継続できる具体的タイムテーブルと調整法の紹介
社労士試験は勉強時間の確保と正しい勉強法で効率よく合格に近づけます。志望者の多くが生活環境や仕事との両立を課題としています。下記の期間別スケジュールを参考に、自分に合った学習計画の立案が重要です。
| 期間 | 総勉強時間 | 週間スケジュール例 |
|---|---|---|
| 半年 | 約600~700時間 | 平日2.5時間/土日4時間 |
| 1年 | 約900~1000時間 | 平日1.5時間/土日3時間 |
| 2年 | 約1200時間 | 平日1時間/土日2時間 |
ポイント
-
自分のライフスタイルに合わせて無理なく続けること
-
週単位で進捗を管理し、遅れには柔軟なリカバリー日を設定
-
模擬試験・過去問演習を時期ごとにスケジュールに組み込む
継続しやすい計画に調整し、働きながらでも着実に学習を進められる体制を整えましょう。
時間効率を上げる勉強のコツと生活習慣改善ポイント – 集中力アップ法、休憩タイミングの科学的根拠、スキマ時間活用術を提示
効率よく学習を進めるには、日々の習慣や勉強法の工夫が必要です。下記の方法を取り入れて勉強効率を最大化しましょう。
時間効率アップのコツ
-
ポモドーロ・テクニックの導入:25分勉強→5分休憩の反復で集中力持続
-
朝やスキマ時間の活用:通勤・昼休みも重要な勉強タイム
-
アウトプット中心の学習:理解→記憶→問題演習のサイクルを徹底
生活習慣の見直しポイント
-
就寝・起床時間を固定して脳の働きを安定化
-
軽い運動や適度なストレッチでリフレッシュ効果を得る
-
甘いものやカフェインで一時的な集中力を補強するタイミングを見極める
短時間の積み重ねでも、効率が高ければ合格に必要な知識は十分定着します。
便利な学習ツール・アプリ活用法とデジタルノート術 – 秒トレアプリやオンライン教材の活用事例、ノート管理術を図解付きで解説
デジタルツールを活用することで、学習効率やモチベーションが大きく向上します。下記の学習アプリやノート活用法は、独学者からの評価も高いものです。
| ツール・アプリ名 | 特徴 |
|---|---|
| 秒トレ(社労士用) | 短時間の問題演習が充実、スキマ勉強に最適 |
| 過去問ランド | 豊富な過去問と解説、間違えた問題の自動管理機能あり |
| OneNote/GoodNotes | ノートのデジタル管理、図解や条文整理に便利 |
| ユーキャン/大原オンライン講座 | テキスト・動画講義・模擬試験がスマホやPCで完結 |
デジタルノート術のポイント
-
条文や論点ごとにセクション分けを明確にし、レビューを効率化
-
問題ごとにミスした箇所を追記し“自分専用の穴埋めノート”を作成
-
ノートアプリに図解やまとめ表を併用し、視覚的理解を深める
アプリとノート術を組み合わせて“アウトプット重視”の学習が可能です。紙とデジタルの長所を活かし、自分専用の「再確認しやすい教材」を構築してください。
状況別おすすめ社労士教材と問題集の選び方
最新テキストランキングと選定基準の詳細解説 – ユーキャン・TAC・フォーサイト他代表的テキストの比較と推奨利用法
社労士試験対策では、信頼できるテキストの選定が非常に重要です。テキスト選びの基準は、改正法対応・わかりやすさ・アウトプット問題の充実度など複数あり、多くの受験生が最新ランキングを参考にしています。特に評価が高いのは次の教材です。
| テキスト名 | 特徴 | 推奨活用法 |
|---|---|---|
| ユーキャン | 初心者向け、全分野解説が丁寧 | まず全体理解から着手 |
| TAC | 出題傾向分析、図表充実 | 科目別総復習が効率的 |
| フォーサイト | カラーテキストで視覚的理解 | 短期間集中学習に最適 |
テキスト選びのポイント
-
改正情報への即応性
-
科目ごとの理解度チェック問題が付属
-
実際の合格者がおすすめする信頼性
独学の場合は、複数のテキストの併用も効果的です。比較しながら自分の理解が深まる教材を軸に毎日学習を重ねていくと着実な進歩が見込めます。
実力アップに必須の過去問集と問題集活用法 – 重要過去問集の特徴と効率的な使い方を段階的に説明
過去問集は社労士試験合格への必須教材です。本試験の傾向分析や弱点把握に役立つため、多くの合格者が重点的に取り組んでいます。
問題集の活用手順
- まずは各科目の基礎事項をテキストで確認
- 出題頻度の高い過去問・良問に優先的に取り組む
- 間違えた問題はノート等にまとめ、反復演習する
- 時間配分や出題形式(択一式・選択式)を意識して実践
代表的な過去問集の特徴
| 問題集名 | 特徴 |
|---|---|
| TAC過去問題集 | 問題数が豊富、解説が詳細 |
| クレアールの一問一答 | 短期間の総復習に最適 |
| 過去問ランド | スマホアプリ対応、移動中活用に便利 |
毎日のスキマ時間にもアプリ型の過去問を活用すれば、記憶の定着も効率的に進みます。難しい問題や何度も間違う論点は、ノート化して集中的に復習することで得点アップにつながります。
通信・オンライン講座向け教材・サービスの特徴比較 – 各講座の教材品質やサポート体制、費用面を具体的数字入りで比較
忙しい社会人や主婦にも人気なのが、通信教育やオンライン講座の活用です。各講座は教材の質やサポート体制、費用面に特徴があり、それぞれに適した選択が重要です。
| サービス名 | 教材の特徴 | サポート体制 | 参考費用(目安) |
|---|---|---|---|
| ユーキャン | 視覚的でわかりやすい | メール・電話・質問対応 | 約89,000円 |
| フォーサイト | カラー教材・確認テスト | 無料質問・進捗サポート | 約59,800円 |
| TAC | 業界最大手の質 | 校舎質問・生講義も選択可 | 約165,000円 |
通信・オンライン講座選びのポイント
-
教材内容の最新性、改正法への対応
-
サポートの充実とレスポンスの早さ
-
価格に対する教材・指導のバランス
時間や場所を選ばず学習できる通信・オンライン講座は、独学が難しい、モチベーション維持に不安がある方にもおすすめです。自分のライフスタイルや費用感に合わせて最適なサービスを選ぶことが、効率的な合格への近道になります。
アウトプット中心で社労士の勉強法を実践する効果的な暗記テクニック
社労士試験は膨大な知識を正確に記憶し、かつ本番で再現できることが合格のポイントとなります。アウトプット重視の学習スタイルを徹底することで、知識定着と実践力アップの両方を狙えます。具体的には、過去問や問題集での繰り返し演習、知識の整理ノートやマインドマップ作成、記憶術と集中力強化の工夫を組み合わせることが効果的です。
過去問高速回転・問題集の苦手克服チェック法 – 苦手問題のピックアップから繰り返し解き直しまでの具体プロセス
アウトプットの王道は過去問・問題集の活用です。苦手分野の分析から反復演習までを以下の手順で進めると効果的です。
- 過去問・問題集を一通り解く
- 間違えた問題・自信がなかった問題は必ずピックアップ
- 苦手分野は専用リストやノートに転記、繰り返し練習
- 数日おきに再度同じ問題を解き、正解できるまで回転する
- 定期的に全体の復習を行い定着度をセルフチェック
下記のような管理表を活用すれば効率的に弱点を克服できます。
| チェック項目 | 状況 | 次回実施日 |
|---|---|---|
| 労働基準法1-2(択一) | 不正解 | 3日後 |
| 年金全体復習 | 要再確認 | 1週間後 |
この徹底した反復が「社労士独学いける」「社労士の勉強法がすごい」と感じる合格力へと直結します。
ノート・マインドマップ活用で理解を深める方法 – 記憶の連結や系統立てに役立つ手法の具体例を紹介
知識を深く理解し系統立てて覚えるにはノートやマインドマップが有効です。ポイントは「真似しやすいシンプルな形」と「連想のしやすさ」。以下の手法をおすすめします。
-
見開きノートでまとめる
- 左側に条文や用語、右側に具体例や注意点を記載
-
マインドマップで全体像を図解
- 法改正や重要テーマは図解で記憶に定着
-
色分け・アイコンを使いメリハリをつける
- 法律ごとに色ペンを使い分ける
- 間違えたポイントに目立つマークを付ける
この「紙一枚勉強法」や「社労士勉強ノート法」なら、苦手分野の洗い出しや再確認も楽になり、独学者はもちろん、忙しい社会人や主婦にもおすすめです。
暗記の質を上げる記憶術と集中力アップのヒント – イメージ連想法、分散学習の実践策など
短時間で効率よく記憶するためには暗記の質の向上が重要です。特に「イメージ連想法」や「分散学習(スプレッドラーニング)」の実践が効果的です。
-
イメージ連想法
- 条文や数字を具体的なイメージ、語呂合わせにして記憶する
- 例:労災保険「1人1冊1週間」→個人事業主要件を語呂とイラストで覚える
-
分散学習(長時間連続より、短時間を複数回)
- 朝夜・通勤時間など隙間に小分けして復習
- 短く繰り返すことで定着率が向上する
さらに社労士専用アプリやウェブサービスを活用すると、移動中や外出先でも効率良く勉強でき、短期間のスケジュールにも対応が可能です。こうした工夫を取り入れることで「何回やっても覚えられない」「勉強がつまらない」と悩むことが減り、楽しみながら成果が出せる学習環境を実現できます。
社労士の勉強法に役立つモチベーション維持と心理面サポート策の実践的アドバイス
人気のモチベーション管理法と目標設定 – 目標を細分化し達成感につなげる進め方のポイント
社労士試験は長期間の学習が必要となるため、途中でモチベーションを失わない工夫が不可欠です。多くの受験生が実践している管理法は、「目標の細分化」です。例えば、「1週間で労働基準法の第1章を理解する」「毎日30分は過去問を解く」など、具体的で達成しやすい小目標を設定すると、日々の達成感が得られ、継続しやすくなります。実際に達成した目標にはチェックを入れたり、手帳やアプリで可視化して進捗を確認する方法もおすすめです。
下記のテーブルは、主なモチベーション管理法とその特徴をまとめたものです。
| 方法 | 特徴 | 使い方の例 |
|---|---|---|
| 小目標の設定 | 達成感・継続力が向上 | 1日1単元ごとに目標を設定する |
| 進捗の見える化 | 頑張りが目で分かりやすい | 学習アプリの活用や手帳に記録 |
| ご褒美の設定 | 学習の動機づけにつながる | 習慣化できた週末に好きなスイーツを食べる |
挫折しないための工夫と仲間作り活用例 – SNSコミュニティや学習会の活用メリット
独学で社労士試験を目指す場合、孤独を感じやすく挫折しやすいため、仲間との交流が有効です。SNS上の社労士受験者向けコミュニティでは、勉強法やテキストの使い方、ノートの取り方などを共有し合えます。オンライン学習会や意見交換の場は情報収集にも役立ち、学習の楽しさや不安の解消につながります。
仲間作りのメリットをリストで紹介します。
-
気軽に質問や疑問を相談できる
-
同じ目標に向かう仲間の姿勢に刺激を受けられる
-
合格体験記や失敗談からリアルな情報を得られる
-
モチベーションの維持がしやすい
このような繋がりが、途中で諦めず最後まで勉強を継続する力になります。
ストレスケア・集中力回復テクニック – 瞑想、軽運動、休憩の科学的根拠を解説
長時間の学習にはストレス管理と集中力回復が重要です。短時間の瞑想や深呼吸は自律神経を整え、思考をリセットできます。また座りっぱなしを避け、合間にストレッチや軽い運動を取り入れることで、血流が良くなり脳のパフォーマンスが向上します。
ポモドーロ・テクニックのように「25分集中+5分休憩」を繰り返す手法は科学的にも集中を維持しやすい方法です。
-
集中力が途切れる前に休憩を入れることで生産性が上がる
-
軽運動やストレッチで心も身体もリフレッシュできる
-
定期的に瞑想やマインドフルネスを取り入れると不安の軽減につながる
自分に合ったストレスケアと集中力の高め方を意識することで、効率的かつ継続的な学習が可能になります。
試験対策に必須の法改正・最新情報確認方法と社労士勉強法での対策
法改正の主なポイントと試験への影響 – 社会保険・労働法関係の重要改正点を詳細に定義
社会保険や労働法分野は、毎年改正ポイントが発生しやすい分野です。例えば、厚生年金保険法や健康保険法の一部改正、育児・介護休業法の見直し、雇用保険制度改正などが挙げられます。出題傾向としては新しい改正点が重点的に問われることが多いため、社労士試験合格を目指す上で、最新法令の把握は欠かせません。法改正に対応できているか否かが得点アップのカギとなります。また、出題形式も法改正部分が択一式や選択式で問われることが増えているため、ポイントごとの最新内容を整理し、過去問と照らし合わせて繰り返し暗記することが効率的です。
最新情報を効率よく追うツール・サービス紹介 – 改正情報メール配信サービスやニュースサイトの活用法
最新の法改正や試験に関する情報を効率的に追うには、信頼できるツールやサービスの活用が不可欠です。下記のサービスが多くの受験生に利用されています。
| サービス名 | 概要 | メリット |
|---|---|---|
| 厚生労働省公式HP | 最新の社会保険・労働法改正情報を随時掲載 | 情報が正確・公式資料で安心 |
| LEcメールマガジン | 試験対応の法改正ポイントをメール配信 | 重要点をまとめて受信できる |
| 社労士受験SNSグループ | 受験生同士で最新情報や体験談を交換できる | 体験情報や独自の着眼点を得られる |
| 資格学校YouTube | 改正点や試験速報を動画で短時間で解説 | 移動中でも視聴・隙間時間活用 |
上記を組み合わせて使うことで、改正情報を漏れなくキャッチできます。自分の学習スタイルに合った情報媒体を選ぶこともポイントです。
法改正対応済み教材リストとアップデート対応例 – 法改正反映の信頼できる教材選定の判断基準
社労士勉強法で特に注意したいのが、法改正にしっかり対応している教材選択です。教材選びを間違えると、不正確な知識で得点を落とすリスクがあります。
教材選定時の判断ポイントとおすすめ例を表にまとめます。
| 教材名 | 法改正対応状況 | 特徴 |
|---|---|---|
| ユーキャン | 改正ごとに最新年度版を発行 | 添削・サポートも充実、初学者にも分かりやすい |
| TACテキスト | 年度ごとにアップデート | 試験範囲を体系的に整理、過去問との連携が強い |
| オートマ社労士 | WEB版で随時法改正反映 | モバイル学習に最適、復習効率が高い |
| みんなが欲しかった社労士シリーズ | 年度版+WEBサポートあり | 図表多用で理解しやすい、重要論点に特化 |
改正速報ページがある教材や、WEBでの法改正情報の提供があるかを必ず確認しましょう。購入後も出版社の公式サイトでアップデート情報をチェックし、常に最新情報で勉強を進めることが合格への近道です。
読者の声を活かした社労士勉強法のリアルな勉強法の紹介
独学合格者のリアルな勉強時間・やり方データ – 詳細スケジュール実例や時間配分、工夫点
社労士試験に独学で合格した方の声から、実践的なスケジュールと勉強法が見えてきます。多くの合格者は、半年から1年間、毎日2〜3時間を確保し、出題範囲の全体像を把握しながら学習を進めています。特に重要なのは以下のポイントです。
-
テキスト精読→ノートまとめ→過去問演習のサイクルを繰り返す
-
苦手科目や論点には時間を多めに割り当て、理解度を意識しながら復習を徹底
-
スケジュール例としては、平日はインプット中心、週末は過去問でアウトプットを重ねる
-
アプリや暗記カードの活用で通勤・隙間時間もフル活用
-
科目ごとの学習進捗をノートや学習計画表で可視化し、モチベーションを保つ
特に「社労士 独学 いける」「社労士 勉強スケジュール 1年」といったキーワードで検索される方の実体験は、多忙な中でも効率よく勉強を続ける方法に直結しています。
講座利用者の選択理由と効果的活用法 – 講座選びの決め手や教材併用方法の具体例
社労士講座の利用者からは、独学との違いを実感する声が多く寄せられます。主な選択理由や活用法を整理しました。
| 受講理由 | 効果的な使い方 | 教材との併用例 |
|---|---|---|
| 法改正・重要点をわかりやすく解説 | 講義動画で疑問点を反復視聴 | テキスト学習で理解不足箇所を重点チェック |
| モチベーション維持がしやすい | 質問サービスで疑問を即時解消 | 講座の模試で本番さながらの演習 |
| スケジュール管理がしやすい | スケジュール表で毎週の学習進捗を可視化 | 市販の過去問集と組み合わせ、解説が足りない箇所を補完 |
多くの受験者は「社労士 勉強方法 おすすめ」「社労士テキストランキング」などを参考にしながら、自分に合った講座と書籍・アプリを組み合わせることで、学習効果を最大化しています。また、予備校の無料教材やアプリ、模試データも積極的に活用することで知識の定着と自信につながった声が目立ちました。
再受験生の失敗回避策と精神的乗り越え方 – 挫折克服の体験談を中心に紹介
再受験する方からは、前回の反省を活かした工夫や気持ちの切り替え方が語られています。失敗を繰り返さないための取り組みは次の通りです。
-
毎日の学習時間の確保を徹底し、少しの時間でも習慣化
-
苦手分野の徹底分析と、ノートやアプリで繰り返し学ぶ
-
受験仲間と進捗を共有したり、SNSやブログで成果を記録してモチベーション維持
-
「何回やっても覚えられない」という悩みには、アウトプット重視の反復練習がおすすめ
-
精神的につらいときには小さな達成目標を設定し、自己肯定感を高める
合格体験談には、「社労士の勉強法がすごい」「社労士人生変わる」といったフレーズも多く見受けられ、多くの再受験生にとって勇気とやる気の源となっています。成功のためには、地道な継続と自分を信じることが何より重要です。