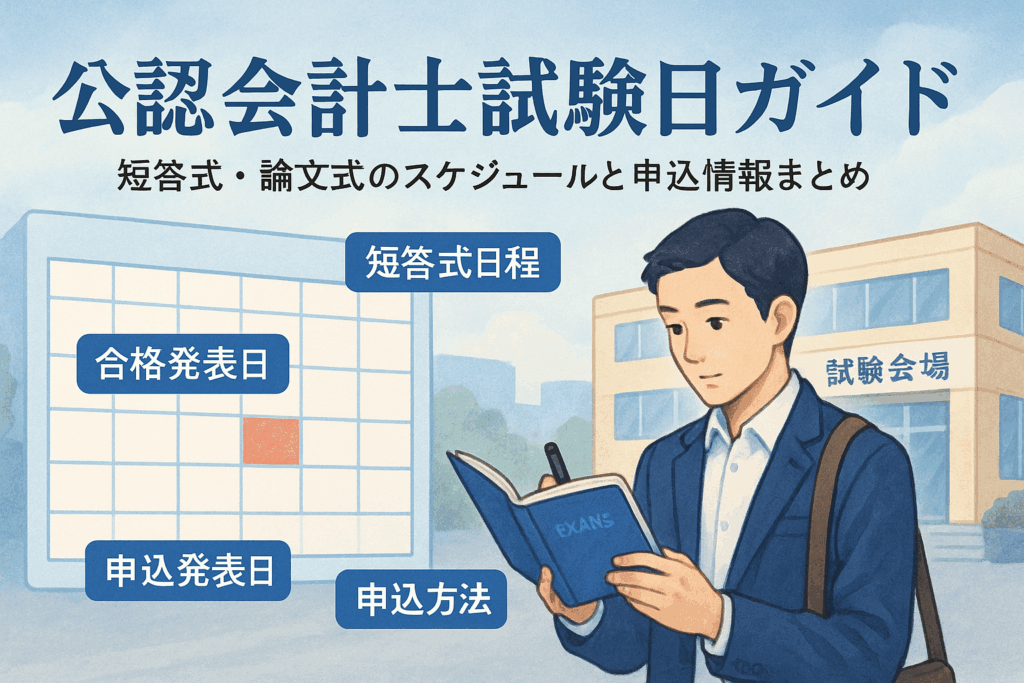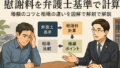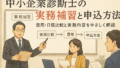「公認会計士試験の日程が毎年発表されると、『短答式・論文式のスケジュールはどう変わる?』『出願や準備に間に合うか不安…』と悩む方は少なくありません。
2025年の公認会計士試験は、第Ⅰ回短答式試験が【2025年5月25日】、第Ⅱ回短答式試験は【2025年12月7日】、そして論文式試験は【2025年8月22日~24日】に実施予定です。出願期間は各回で異なり、直前にはアクセスが集中しやすいため余裕を持った準備が必須です。
さらに、出題傾向や合格率も毎年注目されており、2024年の合格率は短答式【11.3%】、論文式は【10.7%】と発表されました。年ごとに出題範囲や合格者数が変化し、正確なスケジュール把握と対策が合格のカギを握ります。
最新の日程や変化を確実に理解した上で、試験対策の第一歩を踏み出したい方のために、本記事では過去5年の統計・今年度の情報・今後の予測まで網羅しています。
この記事を読むことで、「忙しい中でも効率よく情報収集ができる」「出願ミスや手続き漏れを防げる」と感じていただけるはずです。まずは全体の流れと最新の日程から、安心して受験準備を進めていきましょう。
公認会計士試験日はいつ?試験日程・スケジュールまるわかり|最新年度・過去5年・来年度予測まで網羅
公認会計士試験日2025年の日程・全体スケジュール
公認会計士試験は毎年大きく2つのステージに分かれています。短答式試験は年2回(第Ⅰ回・第Ⅱ回)、論文式試験は年1回実施され、詳細なスケジュールと出願期間が公式に発表されます。実際の試験日や出願期間は年度ごとに微調整があるため、必ず公式情報を確認することが推奨されます。以下のテーブルで2025年度の主要スケジュールを掲載します。
| 試験区分 | 日程 | 出願期間 | 合格発表日 |
|---|---|---|---|
| 第Ⅰ回短答式 | 2024年12月8日 | 2024年8月23日~9月12日 | 2025年1月15日頃 |
| 第Ⅱ回短答式 | 2025年5月25日 | 2025年2月3日~2月25日 | 2025年6月中旬 |
| 論文式 | 2025年8月22日~8月24日 | 短答合格者のみ | 2025年11月下旬 |
会場は主要都市(東京・大阪など)を中心に設定されます。各試験回ごとに会場と時間割が異なるため、詳細は公式サイトでの事前確認が必須です。
短答式試験(第Ⅰ回・第Ⅱ回)の詳細日程と出願期間
短答式試験は公認会計士試験の第一段階に位置づけられており、年2回実施される点が特徴です。2025年では、12月(第Ⅰ回)と翌年5月(第Ⅱ回)に分かれて開催され、どちらかで合格すれば次の論文式試験に進めます。
短答式試験のポイント
- 科目:財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の4科目
- 試験時間:約3時間半
- 出願方法:インターネット出願が主流
第Ⅰ回は前年度秋、第Ⅱ回は冬から春の期間で出願を受け付け、締切を過ぎると申込できません。どちらの回も合格発表が迅速に行われるため、スピーディな対策が重要です。
論文式試験の日程・会場・科目構成
論文式試験は、短答式合格者のみが受験できる公認会計士試験の最終ステップとなります。2025年度は8月下旬の3日間で開催され、全国10カ所以上の主要都市で実施されます。
論文式試験の概要
- 主な会場:東京、大阪、名古屋、札幌、福岡など
- 科目構成:必須科目(会計学、監査論、企業法、租税法)+選択科目(経営学、経済学、民法、統計学など)
- 試験時間:全日程を通じて合計19時間以上
- 合格発表:11月下旬
論文式は記述力と論理力が問われるため、過去問分析と実践的な対策がポイントとなります。
年度間のスケジュール変化と最新動向
公認会計士試験の日程は、過去5年間で大きな変更はありませんが、近年は会場や時間割の最適化が進みました。2025年もほぼ前年通りのスケジュールが継続されています。2026年度以降も同様の時期で実施される見込みですが、社会情勢や制度改定が発表された場合には柔軟な対応が求められます。
各年度の違いを比較することで、学習計画の立てやすさや出願タイミングの見極めにも役立ちます。また、インターネット出願や会場増設など利便性向上の動きも続いており、受験者にとってより参加しやすい試験環境となっています。試験日程や合格発表の時期、会場情報はこまめにチェックし、万全の準備を心がけてください。
短答式・論文式試験の科目・出題傾向・最新対策法
会計士を目指す方にとって、公認会計士試験の科目ごとの出題傾向と効果的な対策法を把握することは非常に重要です。短答式試験と論文式試験はそれぞれ出題分野と対策ポイントが異なるため、最新傾向を押さえて効率的に学習を進める必要があります。下記では、各試験の特徴や最新の動向、具体的な対策ノウハウを詳しく紹介します。
短答式試験科目と対策法
短答式試験は公認会計士試験の最初の関門で、マークシート方式による選択問題となっています。主な科目は以下の4つです。
| 科目 | 概要 | 配点比率 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 財務会計論 | 財務諸表・計算・理論 | 40% | 計算・理論バランスの取れた対策が必要 |
| 管理会計論 | 原価計算・管理会計全般 | 10% | 問題演習の反復で基礎を固める |
| 監査論 | 監査基準・監査実務 | 25% | 体系理解と模試で得点源に |
| 企業法 | 商法・会社法・民法基礎 | 25% | 頻出分野の反復と条文暗記 |
近年は理論・計算両面で出題難度が徐々に上昇しており、教養知識だけでなく実践的な計算力や時間配分の工夫も求められています。
直近3年間の出題傾向の変化と対策ポイント
近年、短答式試験では次のような出題傾向の変化が見受けられます。
- 財務会計論で追加論点や新制度に関連する出題が増加
- 管理会計論で文章問題のボリュームが拡大し、図表分析の対応力が問われる
- 監査論や企業法は法改正に伴う最新知識の比重が増し、暗記だけでなく運用能力が重視
対策として重要なのは、過去問演習を十分に重ねることと、最新の法改正や出題予想にも注目することです。模試で時間を計りながら問題を解いたり、アウトプットの量を増やすことで、合格に直結する実力が身につきます。
論文式試験科目と攻略のコツ
論文式試験は、知識の深さに加え、論理的な記述力が問われる本格的な記述論述形式です。試験科目は以下の通りです。
| 必須科目 | 内容 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 会計学 | 財務会計論・管理会計論 | 理論・計算の総合力が問われる |
| 監査論 | 監査手続・制度関連 | 事例問題や最新の法令に注意 |
| 企業法 | 会社法・商法・民法基礎 | 具体的事例に即した論述が必要 |
| 租税法 | 所得税・法人税など | 判例知識や時事税制の理解が合否を分ける |
| 経済学 | マクロ・ミクロ経済理論 | 基本知識+時事問題対応力 |
選択科目は経営学や民法などから1科目を選択します。各科目とも例年、実業界の動きや社会問題を反映したケーススタディが増加傾向にあります。
合格者が実践する論文式対策・回答作成ノウハウ
論文式の合格者が重視する点は、以下の3つです。
- 答案構成のテンプレート化
問題ごとによく使う論述パターンを確立し、限られた時間でも筋道立った解答が書けるように対策。 - 時事論点・法改正の対応
最新の会計基準や企業法の改正、税制改正など、新傾向に即した知識も整理し、現場で柔軟に理論を展開できる力を養成。 - 自主採点とブラッシュアップ
本番形式を想定した過去問演習を繰り返し、模範解答と比較して表現や誤字脱字を自己チェックする習慣を身につける。
このような学習を徹底することで、論理的かつ的確な記述力が身につき、最終合格を確実にすることができます。
試験申込・インターネット出願の完全ガイド|失敗しないコツ
インターネット出願の手順と注意点
公認会計士試験のインターネット出願は、限られた期間内に正確な手順で進める必要があります。不備や遅延による申込無効を防ぐため、以下の流れを必ず確認してください。
出願手順の基本フロー:
- 公認会計士・監査審査会公式サイトで最新の試験日程と出願開始日を確認
- 専用ページで出願フォームにアクセス
- 必要事項を入力(名前、住所、連絡先、試験区分、希望会場など)
- 必要書類をアップロード
- 受験料の支払い
- 内容を確認し「申込完了」の通知を必ず保存
出願フォームの一時保存や修正機能も活用できますが、入力ミスがないか必ずすべての項目を再確認してください。また、受験する年度や希望する試験区分の選択間違いは、後から修正できない場合があるため注意してください。
出願期間の厳守と締切後の対応
公認会計士試験の出願期間は決まっており、締切を過ぎると一切の申込みが認められません。出願期間中にすべての手続きを完了させることが重要です。
出願期間のチェックリスト:
- 公式サイトで最新の出願期間を確認
- スマートフォンやカレンダーで締切日までのリマインダーを設定
- 提出前日に一度書類や入力内容の最終確認を行う
出願締切を過ぎてしまった場合、いかなる理由であっても次回の試験まで受験できません。メールやシステムトラブルによる遅延も認められないため、余裕を持った手続きを心掛けてください。最新情報は必ず公式発表で確認しましょう。
必要書類の準備と確認ポイント
インターネット出願にはいくつかの書類が必要です。事前に揃えておくことで、スムーズな申込みが可能になります。
よく求められる書類とポイント:
| 書類名 | ポイント |
|---|---|
| 顔写真データ | 直近6か月以内、無帽、無背景で高画質 |
| 最終学歴証明書 | 卒業見込証明書や卒業証明書など。画像データ化が必要 |
| 本人確認書類 | 運転免許証、パスポート、住民票などいずれか1点 |
| 受験料の払込証明 | 支払後の控えデータを忘れず保存 |
各書類はアップロード前にデータ不備や画質を再確認し、必要があれば事前に役所や学校で取得しておくと安心です。提出前にはファイル形式やアップロードの容量制限もチェックし、送信エラーがないか確認してください。
書類不備の連絡が来た場合は、迅速に再提出することで受付が完了します。出願後もメールのチェックは欠かさないように心掛けましょう。
公認会計士試験会場・アクセス・当日の流れ・持ち物一覧
東京・大阪・地方会場の違いと特徴
公認会計士試験の会場は全国主要都市に広がっており、特に東京・大阪では受験者数が多く、広い会場が用意されています。東京は新宿や品川付近の大学や試験専門会場が多く、交通の便が非常に良好です。大阪会場も梅田・本町エリアを中心にアクセスしやすい立地が特徴です。地方会場では交通機関の本数やアクセスが限定的な場合があり、特に遠方から来場する場合は時刻表や所要時間を事前に確認しておくことが重要です。
下記に主な会場の特徴をまとめました。
| 地域 | 主な会場例 | アクセス | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 大学構内・貸ホール | 複数路線利用可 | 収容人数多い、利便性高い |
| 大阪 | 大学・公的施設 | 駅近が多い | 広い設備、混雑注意 |
| 地方 | 地域大学・公民館 | 交通手段限定 | バス・タクシー利用が必要な場合も |
大都市では待合スペースや飲食施設も充実していますが、地方会場では当日の昼食や休憩スポットを事前に把握しておくと安心です。
当日の持ち物チェックリストとトラブル回避法
試験当日は忘れ物が許されません。以下の持ち物リストで事前確認し、早めに準備を済ませておきましょう。
- 受験票:入場時に必須
- 写真付き身分証明書:本人確認
- 筆記用具(HB~B鉛筆・消しゴム)
- 時計(試験会場には時計が設置されていない場合あり)
- 昼食・飲み物
- 上履き(会場による)
- 参考書やノート(休憩中の見直し用)
前夜にお弁当・飲料・交通系ICカードなども準備し、当日は余裕を持ったスケジュールで行動しましょう。当日トラブル対策として、公共交通機関の遅延情報も事前にチェックしておくのがおすすめです。また、会場周辺にコンビニやロッカーがあるかも事前調査しておくと安心です。
会場下見のススメと実体験からの注意点
初めての試験会場に向かう場合、本番前に現地の下見をしておくと大きな安心につながります。駅からの徒歩ルートや、会場入り口、休憩場所など実際に自分の目で確認しておくことで、当日の混乱や遅刻リスクを減らすことができます。
特に乗り換えや駅から会場まで徒歩10分以上かかる場合は、事前にルートを歩いておくとより安心です。また、駅や会場周辺の混雑具合、トイレの位置や自動販売機の有無も事前にチェックしておくと、試験当日に焦らず行動できます。実際に下見をした受験生からは「迷わず余裕を持って会場入りできた」「会場設備の様子が分かり安心できた」という声も多く聞かれます。余裕を持った行動がベストコンディションの確保につながります。
合格発表日・合格率・合格者数推移・合格後の流れ
合格発表日と発表方法の詳細
公認会計士試験の合格発表は例年、試験ごとに決められた日程で公式にアナウンスされます。2025年の論文式試験の合格発表日は11月21日です。短答式試験の場合は、各回ごとに年2回、合格発表日が設定されています。発表方法は以下の通りです。
- 監査審査会および金融庁の公式サイトに掲載
- 受験者の個人ページにて合否通知の公開
- 合格者一覧のインターネット公表(受験番号で照会可能)
合格発表日に関する推移は、近年ほとんど変動がなく、12月と6月に短答式、11月に論文式の発表という流れが確立されています。再検索ワードとして「公認会計士 試験日程 2025 合格発表」や「公認会計士試験 短答式 合格発表日」といった具体的な年号と発表日を知りたい検索が多いことも特徴です。
合格発表日の推移と再検索ワード対応
合格発表日の推移を下記のテーブルで整理します。
| 試験区分 | 試験日 | 合格発表日 |
|---|---|---|
| 短答式 第Ⅰ回 | 2024年12月8日 | 2025年1月中旬 |
| 短答式 第Ⅱ回 | 2025年5月25日 | 2025年6月下旬 |
| 論文式 | 2025年8月22~24日 | 2025年11月21日 |
再検索が多いワードには、合格発表日だけでなく、発表の時間も注目されますが、基本的に正午ごろよりインターネット上で公開されます。ただし閲覧集中時は表示まで時間がかかるケースもみられます。
合格率・合格者数の推移と傾向分析
公認会計士試験の合格率と合格者数は年によって若干の変動がありますが、全体としては一定の水準を保っています。最新のデータを下記にまとめます。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 令和4年 | 10,000 | 1,360 | 13.6 |
| 令和5年 | 10,500 | 1,450 | 13.8 |
| 令和6年 | 11,000 | 1,520 | 13.8 |
| 令和7年 | – | – | – |
合格率はおおむね13%から14%の間で推移し、難関資格であるといえます。受験者数は近年微増傾向にあり、会計・監査業務へのニーズの高まりが影響しています。合格者が増加傾向となる一方で、試験内容や出題科目は大きな変更がないため、安定した合格基準が続いています。
合格後の流れ
公認会計士試験に合格した後は、実務補習所への登録、2年以上の実務経験、実務補習受講、修了考査合格など、資格登録に向けたステップが待っています。流れは次の通りです。
- 合格通知を受領後、公認会計士協会に登録申請
- 実務補習期間(最低2年)と並行して監査法人などで業務経験
- 実務補習所のカリキュラム修了
- 修了考査(最終試験)に合格
- すべての要件を満たしたのち「公認会計士」として正式登録
このプロセスを経て、会計・監査・コンサルティング分野など幅広い分野での活躍が期待されます。合格後の進路や就職に関する相談も、各種サポート機関が情報提供しています。
徹底比較|USCPA・税理士との試験日程・難易度・キャリア展望
USCPA(米国公認会計士)試験日程・内容比較
USCPAの試験は日本の公認会計士と大きく異なり、通年実施されているのが特徴です。受験者は自分のペースで複数回チャレンジが可能なため、キャリアと両立しやすいメリットがあります。試験科目はFAR(財務会計)、AUD(監査)、BEC(企業経営)、REG(税法・倫理)の4科目です。米国基準による出題が中心で、英語力も問われます。下記のテーブルで日本の公認会計士との主な違いを比較します。
| 項目 | 日本の公認会計士 | USCPA |
|---|---|---|
| 試験実施回数 | 年2~3回(短答・論文) | 通年(随時) |
| 受験資格 | 学歴・単位要件あり | 州による(柔軟な要件) |
| 試験形式 | 短答式・論文式 | CBT(コンピューター) |
| 科目 | 財務会計論・管理会計論・監査論等 | FAR/AUD/BEC/REG |
| 言語 | 日本語 | 英語 |
| 合格率 | 約10~15% | 30~50% |
| キャリア | 日本国内の監査法人など | 海外・外資系企業等 |
公認会計士とUSCPAの違い・各資格のメリット・デメリット
日本の公認会計士は国内での圧倒的な信頼性と独占業務が強みです。合格者は監査法人・一般企業で活躍しやすく、資格そのものの社会的評価が高いのが特徴です。一方、試験の難易度が非常に高く、学習期間も長期化しがちです。
USCPAはグローバルな資格であり、海外・外資系のキャリアや会計分野での汎用性が魅力です。試験は合格率が高めで受験機会も多く、社会人のキャリアチェンジに適しています。ただし国内独占業務はなく、英語力や国際基準の会計知識が必要です。
- 公認会計士(日本)
- 強み:独占業務、国内での信頼性、伝統的な地位
- 注意:難関・長期化、学歴要件、受験生の競争
- USCPA
- 強み:国際キャリア、柔軟な試験日程、比較的短期間
- 注意:英語必須、国内での独占業務不可
税理士試験との日程・難易度・キャリア比較
税理士試験は毎年7月下旬に実施され、1科目から受験することが可能です。科目合格制を採用しており、複数年かけて5科目合格を目指す戦略的な学習が可能です。公認会計士試験は年2回の短答式、年1回の論文式で、全科目一括合格が基本となります。公認会計士資格があれば、税理士登録も可能です。
| 項目 | 公認会計士 | 税理士 |
|---|---|---|
| 試験日程 | 年2回(短答式)・年1回(論文式) | 年1回(7月、科目合格制) |
| 合格率 | 10%前後 | 15%前後(科目により変動) |
| 必要科目 | 5~7科目 | 5科目(簿記、財表、選択可) |
| 難易度 | 極めて高い | 高いが科目ごと受験可能 |
| キャリア | 監査法人・企業・独占業務 | 税理士事務所・独立開業 |
税理士は科目合格制のため、社会人や働きながら長期計画で資格取得を目指しやすい傾向があります。公認会計士は一発試験型で、難関でありながら合格後のキャリアパスが非常に広い点が魅力です。
資格取得後のキャリアも大きく異なり、公認会計士は国内外問わず監査や会計コンサルティング領域で幅広く活躍できます。税理士は税務の専門家として独立開業や中小企業の顧問業務での実績を築くことが可能です。
最新の試験制度変更・今後の動向・将来予測
直近の試験制度変更と影響
直近では、公認会計士試験の日程や実施方式に複数の変更が加えられています。令和7年(2025年)の試験では、短答式試験が年2回、論文式試験が年1回実施されるスケジュールが継続されている一方で、出願方法や試験会場の利便性向上も進行中です。オンライン出願が基本となり、受験者の手続き負担が軽減されました。試験会場も主要都市に拡大され、東京・大阪だけでなく、地方からのアクセス性も向上しています。
以下は、近年の主な制度変更点を一覧でまとめたものです。
| 変更内容 | 詳細/影響 |
|---|---|
| オンライン出願 | 紙での郵送から完全オンライン化へ。手続きが容易に |
| 会場拡大 | 主要都市に加え地方会場も設置。受験者の利便性向上 |
| 試験科目のバランス | 会計・監査・租税・法務等、出題比率の最適化 |
| 合格発表の迅速化 | 採点プロセス改善で、結果公開までの期間短縮 |
制度変更によって、各回の難易度や出題形式に微調整が施されていることにも注意が必要です。
今後の試験日程・難易度・出題傾向の予測
公認会計士試験の今後のスケジュールや傾向についても動向を押さえましょう。2026年・2027年の試験日程も例年通り、短答式は5月・12月、論文式は8月下旬に実施される見通しですが、社会情勢や制度改正によって一部の実施日や合格発表日が変動する可能性があります。
今後の注目ポイントは次の通りです。
- 試験内容の複合化 財務会計論・管理会計論・監査論などの会計分野だけでなく、民法や経営学など幅広い科目が重視される
- 記述・応用問題の強化 理解力や実践力を問う出題が増加傾向
- デジタル対応科目や最新企業事例の導入 企業のデジタル化や会計基準の変化に関連する内容も反映
負担増となる部分もありますが、将来の会計・監査分野で即戦力となる人材を育成する意図があります。受験者は公式発表の試験日程や合格発表日だけでなく、出題傾向と時間配分、必要な対策にも注意を払いながら、計画的に学習を進めることが大切です。
過去5年・来年度予測の試験日程・合格発表日一覧表
公認会計士試験は、毎年短答式試験と論文式試験が実施されており、それぞれの試験日程や合格発表日が公表されています。最新年度の情報から今後の予測までを含めて、過去5年分と来年度のスケジュールをわかりやすく一覧表にまとめました。下記の表では、短答式試験(第Ⅰ回・第Ⅱ回)、論文式試験、各合格発表日を比較して確認することができます。公認会計士を目指す方は、計画的な受験準備のために最新の情報を常にチェックしておきましょう。
| 年度 | 第Ⅰ回短答式試験 | 第Ⅰ回短答合格発表 | 第Ⅱ回短答式試験 | 第Ⅱ回短答合格発表 | 論文式試験 | 論文式合格発表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 12月11日 | 1月20日 | 5月29日 | 6月22日 | 8月19-21日 | 11月18日 |
| 2023 | 12月10日 | 1月19日 | 5月28日 | 6月21日 | 8月18-20日 | 11月17日 |
| 2024 | 12月8日 | 1月17日 | 5月26日 | 6月20日 | 8月23-25日 | 11月15日 |
| 2025 | 12月7日(予定) | 1月16日(予定) | 5月25日(予定) | 6月19日(予定) | 8月22-24日(予定) | 11月21日(予定) |
| 2026 | 12月中旬(予想) | 1月中旬(予想) | 5月下旬(予想) | 6月下旬(予想) | 8月下旬(予想) | 11月中旬(予想) |
上記のスケジュールは現時点の発表および過去の傾向に基づきまとめています。受験に必要な出願期間や詳細な日程については、必ず公式の発表で随時確認してください。
年度ごとの試験日程・合格発表日比較
ここでは各年度ごとの試験日と合格発表日を比較し、時期の違いや傾向を解説します。
- 短答式試験は原則として毎年「5月末(第Ⅱ回)」および「12月上旬(第Ⅰ回)」に実施されています。
- 合格発表は試験から約1か月後と設定されており、スピーディーなフィードバックが得られるのが特徴です。
- 論文式試験は毎年8月下旬に3日間行われ、合格発表は11月中旬から下旬となっています。近年は全体的に日程が一定しており、受験計画が立てやすい傾向です。
年度ごとの日程を比較することで、自身の学習スケジュールや試験準備期間がイメージしやすくなります。
来年度(2026年)試験日程予測・確定情報
2026年の公認会計士試験については、現時点では確定情報は発表されていませんが、過去の推移をもとに下記のスケジュールが予想されます。
- 第Ⅰ回短答式試験:2026年12月中旬実施が見込まれます。出願期間はおおよそ8月下旬~9月中旬と予測されます。
- 第Ⅱ回短答式試験:2026年5月下旬の実施が濃厚です。出願期間は2月上旬~2月下旬になる見込みです。
- 論文式試験:2026年8月下旬に指定の会場で実施される可能性が高いです。
- 合格発表:短答式はそれぞれ1か月後、論文式は11月中旬から下旬が予測されます。
公式情報が発表され次第、最新日程や出願方法、会場情報等の詳細を必ず確認してください。会場は東京・大阪など主要都市のほか、受験者数に応じて全国の指定会場が設定される傾向にあります。
受験準備を進めるうえで、最新のスケジュール管理と出願期間の把握が合格への近道です。余裕をもってスケジュール調整を行いましょう。
受験生のための年間勉強計画・体験談・合格までのロードマップ
年間勉強計画の立て方と実践例
公認会計士試験に合格するためには、明確な年間スケジュールを組み立て、効率的かつ計画的な学習が欠かせません。まずは短答式・論文式試験それぞれの試験日程を把握し、逆算して学習計画に落とし込むことが重要です。試験対策の進捗を管理するうえで、月ごと・週ごとの到達目標を明確にしておきましょう。
長期的な学習計画の一例をテーブルで示します。
| 時期 | 重点対策内容 | 勉強時間の目安 |
|---|---|---|
| 4〜8月 | 基本科目のインプット、過去問分析 | 平日3〜4時間、休日6時間 |
| 9〜11月 | 応用問題、模試受験 | 平日3.5〜4.5時間、休日6〜8時間 |
| 12月 | 短答式試験直前対策 | 集中強化(平日5時間以上) |
| 1〜3月 | 論文科目の基礎・例題演習 | 平日3時間、休日5〜6時間 |
| 4〜7月 | 論文式過去問・答練 | 平日4時間、休日7時間 |
| 8月 | 論文式試験本番 | 調整(体調管理重視) |
年間を通じて、定期的な模試で実力を測り、弱点分野の重点学習に時間を充てることがポイントです。スキマ時間を活用して理論暗記や計算問題に触れると効率的です。
合格者の1日のスケジュールと体験談
合格者が実践していた1日のスケジュールをみていきます。フルタイムの学習者から働きながら合格を目指した受験者まで、各自のライフスタイルに合わせて勉強計画を組み立てることが現実的です。
| 時間帯 | 主な活動内容 |
|---|---|
| 6:00〜7:00 | 朝の準備・通勤、移動中に理論暗記 |
| 8:00〜12:00 | 各科目のインプット学習や計算演習 |
| 12:00〜13:00 | 昼食・休憩 |
| 13:00〜18:00 | 問題演習・論文対策 |
| 18:00〜19:00 | 夕食・リフレッシュ |
| 19:00〜22:00 | 模試復習・弱点分野の補強 |
合格者の体験談から、「朝の演習で頭を活性化」「夜は自習室で集中力を維持」といった声が多く上がっています。また、模試後には必ず復習の時間を確保し、本番に向けて不明点を解消していくことが重要とされています。
社会人合格者は仕事の後や出勤前の時間、週末を最大限活かして学習。合格までの平均勉強期間は2〜3年が多く、生活リズムを崩さずに計画を貫いたことが合格への近道です。
こうした実践例を参考に、自分に合った計画と日単位のルーティンを整えることが、着実な合格への第一歩となります。