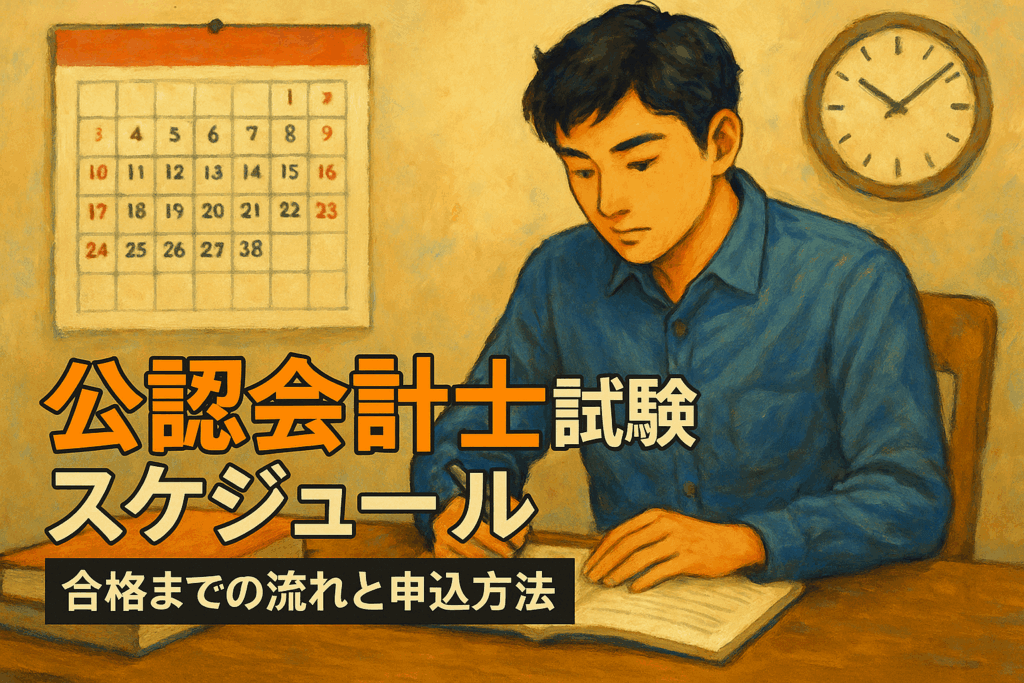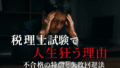【2026年の公認会計士論文式試験、申込期間や試験日を正確に把握できていますか?】
今や論文式試験の受験者数は年々増加し、近年では毎年【約5,000人】以上が挑戦しています。しかも、正しい日程や出願のタイミングを一度でも見逃すと、1年を無駄にするリスクが避けられません。
「公式の申込締切をうっかり過ぎてしまった」「短答式との連動や資格要件が複雑で混乱した」という声も多く、情報の見落としが【不合格】【費用と時間の損失】につながるのが現実です。
本ページでは、【令和8年(2026年)】論文式試験の正確な日程・申込締切・合格発表日を全網羅。さらに、申込方法・試験科目別スケジュール、会場案内、過去問・模試活用まで、合格に直結するポイントを余さず分かりやすく解説しています。
ここで得られる最新スケジュール情報を活用することで、「知らずに損した…」と後悔するリスクを徹底回避可能です。
最後まで読むことで、抜けや漏れなく効率的に受験準備を進められます。まずは、あなたの不安や疑問をすべて解決できる内容をチェックしてみてください。
- 公認会計士の論文式試験の日程と年間スケジュール詳細 – 最新の正確な日程と申込期間を網羅
- 論文式試験の詳細な時間割と試験科目 – 効率的な時間管理のために
- 申込方法・出願手続きの具体的フローと書類準備 – 申込漏れを防ぐために
- 合格発表のスケジュールと閲覧方法 – 合格後の手続きもわかりやすく
- 過去問活用と模試スケジュール – 効果的に論文式試験対策を進める
- 試験会場情報・持ち物リスト – 試験当日に安心して臨むために
- 効果的な勉強スケジュールの立て方 – 時間管理と科目別優先度
- 最新動向と制度変更のポイント – 試験制度改定に備えるために
- 公認会計士の論文式試験に関するよくある質問(Q&A) – 受験者の疑問を一挙解決
公認会計士の論文式試験の日程と年間スケジュール詳細 – 最新の正確な日程と申込期間を網羅
公認会計士の論文式試験は、資格取得を目指す方にとって大きな節目となる重要な試験です。正確な日程把握とスケジュール管理が合格への第一歩となります。ここでは、公認会計士論文式試験の最新の日程、申込期間、短答式試験との連携について詳しく解説します。
論文式試験の実施時期と年間スケジュール – 短答式試験との関係も含めた全体像解説
公認会計士試験は主に短答式と論文式の2段階で構成されています。論文式試験は通常、毎年8月下旬に3日間かけて実施されます。受験には直近の短答式試験合格が基本条件となっており、計画的な学習と出願手続きが重要です。
下記のテーブルで、主な年間スケジュールを分かりやすくまとめました。
| 項目 | 予定時期 | 備考 |
|---|---|---|
| 短答式試験第1回 | 12月中旬 | 受験で翌年の論文式受験権獲得 |
| 短答式試験第2回 | 5月下旬 | 論文式受験直前の最終機会 |
| 論文式試験 | 8月下旬(3日間) | 主要会場で実施 |
| 合格発表 | 11月下旬 | 公式サイト等で発表 |
年間を通じてスケジュールを管理し、受験資格を見落とさないことが合格へのカギとなります。
令和8年(2026年)論文式試験の日程・申込締切・合格発表日
令和8年(2026年)の論文式試験は、例年通り8月下旬の3日間に実施される予定です。受験の申し込みは5月下旬から6月中旬が主流で、日程の詳細は以下の通りです。
| 内容 | 日程(目安) |
|---|---|
| 申込受付 | 2026年5月下旬~6月中旬 |
| 試験実施日 | 2026年8月21日~23日 |
| 合格発表 | 2026年11月下旬 |
申込はインターネット出願が基本となっており、期間内での手続き完了が必須です。出願ミスや遅延を避けるため、事前準備や公式情報のチェックを徹底しましょう。
短答式試験との連動性と受験資格のポイント
論文式試験の受験には短答式試験の合格が必要です。短答式試験は年2回、12月と5月に実施されており、論文式の受験資格を得るためには、直近の短答式合格が求められます。
受験資格ポイント
-
短答式試験合格者のみ論文式試験に出願可能
-
短答式試験の結果により、論文式出願手続き時に合格証明が必要
-
科目免除などがある場合は、必要書類を確実に用意
短答式試験と論文式試験は年間スケジュールの中で密接に関係しているため、効率的なスケジュール管理が重要です。最新の公式発表を必ず確認し、漏れなく受験準備を進めましょう。
論文式試験の詳細な時間割と試験科目 – 効率的な時間管理のために
各日程の開始時間・終了時間と休憩時間の概要
公認会計士論文式試験は3日間にわたり実施され、それぞれの科目が時間帯ごとに分かれています。各日のスケジュールに沿って効率的に時間配分を行うことが重要です。
| 試験日 | 開始時間 | 終了時間 | 休憩時間 | 主な科目 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9:00 | 17:30 | 昼休憩60分・各科目間15~20分 | 会計学・監査論 |
| 2日目 | 9:00 | 17:30 | 昼休憩60分・各科目間15~20分 | 企業法・租税法 |
| 3日目 | 9:00 | 16:30 | 昼休憩60分・各科目間15分 | 選択科目・経営学など |
-
各科目ごとにまとまった休憩が設けられており、集中力を維持しやすい構成です。
-
試験時間割は事前に発表されるので、直前まで公式発表を必ず確認しましょう。
科目ごとの出題形式と配点バランス
各科目は主に記述式問題が中心で、思考力や実践的な知識が求められます。配点バランスを理解することで、学習効率が格段に向上します。
| 科目 | 出題形式 | 配点割合 |
|---|---|---|
| 会計学 | 記述・計算 | 30% |
| 監査論 | 記述 | 15% |
| 企業法 | 記述 | 15% |
| 租税法 | 記述 | 10% |
| 選択科目 | 記述・計算 | 15% |
| 経営学 | 記述 | 15% |
-
会計学は最大配点であり、重点的な対策が不可欠です。
-
他の科目もバランスよく点を積み重ねることが合格への鍵です。
選択科目の種類と配点、選択基準の解説
選択科目は受験者が自らの専門性や得意分野に合わせて選べます。主な選択科目には「経営学」「経済学」「民法」などがあります。各選択科目の配点は全体の15%前後であり、合格には確実な得点が必要です。
| 選択科目 | 配点 | 特徴・選択のポイント |
|---|---|---|
| 経営学 | 15% | 経営戦略や組織論に強い方に適する |
| 経済学 | 15% | 数学・グラフ分析に抵抗がない方に有利 |
| 民法 | 15% | 法律知識の応用が得意な受験者に最適 |
-
自分の知識や勉強時間に合わせて科目を選ぶのが成功のカギです。
-
選択科目の過去問を分析し、相性の良い分野に絞って計画的な学習を進めましょう。
申込方法・出願手続きの具体的フローと書類準備 – 申込漏れを防ぐために
公認会計士論文式試験の出願には、厳密な手続きと書類準備が求められます。申込ミスや期限切れを防ぐには、手続きを正確に理解し、必要書類を早めに揃えることが重要です。特にインターネット出願の場合は、操作ミスやデータ未送信などのトラブルも見られます。下記で出願手続きの流れやポイントを整理します。
インターネット出願の手順と注意点
インターネット出願は、多くの受験者が利用する方法です。以下の流れと注意点を確認してください。
- 公認会計士・監査審査会の公式サイトにアクセスする
- マイページに登録・ログイン
- 志願情報や個人情報を正確に入力
- 証明写真データや証明書のPDFをアップロード
- 受験料を指定方法で支払い
- 申込み内容を最終確認し、送信ボタンを押して手続きを完了
- 登録メール宛に申込完了通知が届いたか必ずチェック
特に写真データの不適切なアップロード、入力ミス、支払い漏れが多発しやすいポイントです。申込期限直前はサーバー混雑でアクセスしづらくなる事もあるため、余裕を持った早期出願が推奨されます。
書面出願の方法と提出期限
インターネット環境がない場合や、特別な事情のある方は書面による出願も可能です。必要な申込書類を取り寄せ、下記の流れで手続きします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申込期間 | 公式日程内(例:2025年の場合2月初旬~2月下旬)に必着 |
| 提出書類 | 出願申込書、写真(規定サイズ)、各種資格証明書、返信用封筒など |
| 提出方法 | 書類一式をまとめて郵送、簡易書留や速達推奨 |
| その他 | 必ず控えのコピーを取っておく |
提出書類に不備がある場合、申込が受理されないので、封入前に内容を再確認してください。公式の提出期限を1日でも過ぎると受付不可となります。余裕を持った郵送準備が大切です。
出願時によくあるミスとその回避策
出願時には以下のようなミスが多く見受けられますが、事前にしっかりチェックすることで防げます。
-
写真サイズや形式が指定外
-
申込内容の入力ミスや記載漏れ
-
受験料の納付漏れや誤送金
-
書類の一部未提出や添付漏れ
【対策リスト】
-
必要書類と提出フォーマットを事前に一覧でメモし、不足がないか確認
-
入力・記入後は内容を2回以上見直す
-
提出前に家族や第三者にも確認してもらう
-
早めの手続きで、締切直前の混雑や郵送遅延を回避
-
公式マイページや問合せ先を控えておき、不明点は早めに相談
これらのポイントを押さえることで、安心して公認会計士論文式試験の出願手続きを完了できます。
合格発表のスケジュールと閲覧方法 – 合格後の手続きもわかりやすく
合格発表日と発表形態(オンライン等)
公認会計士論文式試験の合格発表は、例年11月下旬に公表されます。合格発表日は日本公認会計士協会や金融庁の公式ページにて案内され、受験生は期日を逃さず確認することが重要です。
発表形態は近年、主にオンラインで行われており、下記の方法が主流です。
-
公認会計士試験ホームページ上で合格者番号一覧を掲載
-
会場掲示や書面通知は基本的に実施されていない
-
合格者には郵送にて正式な通知が届く場合がある
発表当日はアクセス集中による混雑も想定されるため、事前に公式発表時間や発表ページを確認しておくと安心です。
合格発表の主な確認方法
| 発表方法 | 詳細内容 |
|---|---|
| インターネット発表 | 公式サイトで合格者番号を一覧掲示 |
| 合格通知の郵送 | 合格者宛に後日書面で正式通知が届くことあり |
合格者番号の確認方法と公式発表の信頼性
合格発表当日、受験番号の一覧が公式サイトに公開され、受験生は自身の番号の有無で合否を確認します。番号は昇順で一覧表示されるため、あらかじめ受験票を手元に準備しましょう。
合格番号一覧の閲覧方法
-
公式ページから「論文式試験合格発表」ページにアクセス
-
自分の受験番号を正確に確認
-
掲載は数カ月閲覧可能な場合が多い
この発表は、試験審査会や日本公認会計士協会から公的に発信されるため、誤りがありません。SNSなど非公式情報ではなく、必ず公式発表を参照することが大切です。
合格後の受験後手続きと資格登録
合格後は公認会計士としての登録手続きが必要です。手続きに進む際は、合格通知に記載された案内をもとに、必要な書類(本人確認書類・写真・申請書類)を揃え、指定の期限内に協会や監査審査会へ提出します。
公認会計士登録の主な流れ
- 合格発表後に合格通知・案内を確認
- 登録申請書や必要書類の準備
- 期限までに書類一式を提出し審査を受ける
- 登録完了後、公認会計士証票を受領
資格登録は将来の就職や独立にも大きく関わるため、不備や遅延のないよう着実に進めることが重要です。各手続きや提出書類に関する疑問点は、協会や金融庁の公式案内を参考にしてください。
過去問活用と模試スケジュール – 効果的に論文式試験対策を進める
過去問の入手方法と出題傾向の把握
公認会計士論文式試験に向けては、過去問を効果的に活用することが非常に重要です。過去問は日本公認会計士協会や主要な資格予備校(TAC、大原など)の公式サイトで公開されています。下記のような点に注目し、計画的に確認しましょう。
-
試験科目ごとに年度別の過去問・解答例を一覧でダウンロードできる
-
問題傾向の変化や出題頻度の高い論点をデータで分析できる
-
解説講座や既出問題集を活用し繰り返し学習することで知識の習得を深める
過去問の出題傾向としては、監査論・会計学・企業法・租税法など主要科目で実務的な事例や応用力を問う問題が増加傾向にあります。毎年の改正事項や新たなトピックも盛り込まれるため、最新の出題情報にも目を配ることが欠かせません。
公認会計士論文式試験模試の種類と開催日程
論文式試験対策の柱となる模試には、さまざまな種類があります。主な模試は次のテーブルの通りです。
| 模試名称 | 主催 | 主な開催時期 | 特長 |
|---|---|---|---|
| 直前全国公開模試 | TAC | 6~7月 | 出題傾向を忠実に再現、全国規模の成績判定 |
| 直前答練 | 大原 | 6~8月 | 実戦形式で本番力を鍛える構成 |
| スタンダード模試 | LEC | 5~6月 | 主に個別科目ごとの演習、時間配分重視 |
| 校内模試 | 予備校各校 | 年間数回 | 教材範囲の習熟度を定期測定、個別指導に活用 |
これらの模試は※試験日程や科目免除情報を考慮してスケジュール管理することが重要です。オンライン受験にも対応する模試が増えており、通学が難しい場合でも受験機会を確保できます。
模試の利用メリット・効果的な活用術
模試を受験することで得られる主なメリットは以下の通りです。
-
本番さながらの時間割・出題形式・出願ペースで実力を客観的に測定できる
-
全国レベルでの順位や分野別の弱点が把握できる
-
回答用紙の記入練習や制限時間内の答案作成を体感できる
効果的に模試を活用するには、受験結果をもとに復習を徹底することが大切です。たとえば、誤答や不正解部分を「なぜ間違えたか」まで振り返り、自分なりのノートを作成する習慣が得点力向上に直結します。さらに、模試は出願期間や本試験日程の管理にも役立つため、受験計画の軸として組み込むと良いでしょう。
試験会場情報・持ち物リスト – 試験当日に安心して臨むために
試験会場の所在地・アクセス解説
公認会計士論文式試験は、全国の指定された会場で実施されます。主な会場は札幌、東京、名古屋、大阪、福岡など大都市圏を中心に配置されており、受験票に記載された会場が試験当日の試験場となります。会場には公共交通機関でのアクセスが推奨されており、試験会場の位置や経路は事前に必ず確認してください。
次のポイントを押さえることで余裕を持って移動できます。
-
受験票到着後、会場名と最寄駅を必ず確認
-
駅から会場までの徒歩ルートを予習
-
交通機関の運行状況も試験日前日にチェック
-
車での来場は禁止の会場が多いため注意
試験当日に慌てることの無いよう、到着予定時刻は余裕を持って設定しておくのがおすすめです。
受験票の受け取り方法と持参物チェックリスト
受験票は事前に郵送またはインターネット出願マイページ等からダウンロードして印刷する形式です。試験当日は必ず受験票を持参し、本⼈確認が実施されるため写真付きの身分証明書も用意してください。
下記は必携品のリストです。
| 持ち物 | 備考 |
|---|---|
| 受験票 | 必ず原本またはダウンロード印刷物 |
| 写真付き身分証明書 | 運転免許証、パスポート等 |
| 筆記用具 | HB鉛筆、消しゴム、ボールペン等 |
| 腕時計 | 試験会場内の時計設置が無い場合あり |
| 昼食・飲み物 | 長時間の試験に備えて |
| 上履き | 会場によっては持参指示がある場合も |
上記に加え、各自で必要な品(メガネ、常備薬等)も忘れずにご準備ください。
試験当日の注意事項と禁止物品の詳細
試験当日は、受験票記載の集合・着席時間を厳守してください。遅刻者は、規定により入場できない場合や解答時間が短縮される可能性があります。また、試験開始前に持ち物検査が行われるため、禁止物の持ち込みには十分注意しましょう。
禁止されている主な物品は以下の通りです。
-
スマートフォン、携帯電話などの通信機器
-
ICレコーダー、電子辞書、スマートウォッチ等の電子機器
-
参考書、ノート、カンペ・メモ
-
音の出る時計やタイマー
-
その他、運営側が不適切と判断するもの
これらは禁止物として厳しくチェックされます。不正行為が発覚した場合、失格や今後の公認会計士試験の受験資格停止につながることもあります。安心して試験に専念できるよう、前日までに持ち物を再度見直し、準備を徹底しましょう。
効果的な勉強スケジュールの立て方 – 時間管理と科目別優先度
公認会計士論文式試験では、多岐にわたる科目を体系的に学ぶ必要があり、効率的な勉強スケジュールの構築が合格への鍵です。試験日程から逆算し、出願期間や試験日、各科目ごとの出題傾向を基準に計画を練りましょう。特に論文式の場合、短答式試験の合格者や過去問分析なども情報収集のポイントです。直前期はアウトプット中心に時間を配分し、昼夜のリズムを整えることで本番と同じ時間帯のパフォーマンスを最大化することが重要です。
論文式試験合格に必要な平均勉強時間の目安
論文式試験合格を目指す場合、必要な総勉強時間は個人差はあるものの、一般的には2,000〜3,000時間を確保することが望ましいとされています。社会人や学生などライフスタイルに合わせて、1日2〜6時間の勉強時間を安定して確保しましょう。下記のテーブルは科目別の優先度と推奨勉強時間を一覧にまとめたものです。
| 科目名 | 推奨勉強時間割合 | ポイント |
|---|---|---|
| 会計学 | 35% | 基本を徹底し応用まで網羅 |
| 監査論 | 20% | 理論と事例問題のバランス |
| 企業法 | 15% | 判例の確認と条文理解が重要 |
| 租税法 | 10% | 計算力と法令理解の両立 |
| 選択科目 | 20% | 得意分野の強化と過去問分析 |
計画的に学習進捗を管理し、直前期は模擬試験や過去問演習に時間を投下するのが合格のポイントです。
苦手科目対策と効率的な科目別勉強計画
苦手科目の克服には、学習記録をつけて進捗を可視化する方法が効果的です。毎週の振り返りで、理解が浅い分野をリストアップし、以下の手法を実践しましょう。
-
苦手科目は1日の最初や集中力の高い時間帯に学習
-
過去問や問題集で頻出テーマを繰り返し解く
-
オンライン講座や専門書を活用し理解を深める
-
難問はすぐに質問できる環境(講師・SNSなど)を用意
効率的な学習ステップを定着させることで、全体の得点力アップが期待できます。
モチベーション維持のテクニックとメンタル管理
長期戦の公認会計士論文式試験では、日々のモチベーション維持が重要です。具体的には次の方法を取り入れると効果的です。
-
目標達成シートやカレンダーで進捗を「見える化」
-
小さな目標設定と達成ごとに自分をしっかりと褒める
-
勉強仲間との情報交換や励まし合いで孤立を避ける
-
健康管理や適度な休憩を取り入れ、集中力を持続
また試験前日は十分な休息をとり、当日は日常通りの生活リズムを心掛けることがパフォーマンスの最大化につながります。
最新動向と制度変更のポイント – 試験制度改定に備えるために
2026年に公認会計士論文式試験の制度変更が予定されており、受験生や関係者にとって大きな転換期となります。試験日程や方式の見直しは合格率や受験者動向に影響が出るため、最新情報の把握が欠かせません。これから受験を検討される方は、公認会計士試験の日程や出願情報、合格発表時期などにも目を配ることが大切です。
変更内容やスケジュールの詳細は公式発表をもとに随時確認しましょう。特に、インターネット出願や会場の選択方法、論文式試験科目の範囲改定などがポイントとなります。着実な受験準備には、試験時間割や過去問情報も早めに収集しておくことをおすすめします。
2026年の試験制度改定の概要
2026年度の試験制度では、論文式試験の日程や実施時間、出題範囲の一部見直しが計画されています。主なポイントは以下の通りです。
-
論文式試験の試験日が例年の8月から変更される可能性あり
-
科目構成や出題範囲の調整を予定
-
インターネット出願手続きの利便性向上
-
試験会場割り当ての柔軟化
日程や時間割の変更は受験対策スケジュールに直結するため、公式発表の最新情報に注目しましょう。特に短答式試験と論文式試験の切り替えタイミング、申込期間にも注意が必要です。
過去の合格率推移と受験者動向の分析
直近数年の合格率推移を見ると、受験者数の増減や試験科目の難易度変更が結果に影響しています。
| 年度 | 論文式受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,200 | 1,400 | 17.1 |
| 2024 | 7,950 | 1,350 | 17.0 |
| 2025 | 7,700(予測) | 1,300(予測) | 16.9(予測) |
このデータから読み取れるのは、制度改定を控えた年は受験者数がやや減少し、合格率には大きな変動が見られない点です。今後も試験制度や日程に敏感に対応し、適切な学習計画と情報収集を心がけることが重要です。
今後の試験スケジュール予測と注意点
試験制度改定を見据えて、2025年・2026年の公認会計士試験は、スケジュールの柔軟化と申込方法のデジタル化が進むと考えられます。
主なスケジュールのポイントは以下の通りです。
-
2025年短答式試験は12月・翌年5月に実施予定
-
2026年論文式試験の日程は8月から秋以降になる可能性
-
インターネット出願期間や手順の変更
-
合格発表時期も例年よりずれる場合あり
特に、試験日程や出願期間が例年と異なる場合は、公式発表を必ずチェックしましょう。会場の選択や持ち物、時間割の変更にも対応できるよう、最新情報の入手と確認を心がけてください。計画的な受験準備と細やかな情報収集が、合格への近道となります。
公認会計士の論文式試験に関するよくある質問(Q&A) – 受験者の疑問を一挙解決
出願方法や申込期限に関する質問
公認会計士の論文式試験の出願は、主にインターネット出願が利用されています。出願期間は年度によって異なるため、最新の試験公表情報を必ず確認してください。インターネット出願の際には必要書類の準備が不可欠です。例えば短答式試験合格証明や、本人確認書類などが要求される場合があります。申し込み期限を過ぎると受験できないため、余裕をもって申請することが大切です。
出願手続きにおける主な注意点は、登録完了メールや受験票の受け取りの有無を必ず確認することです。試験手数料の納付方法も年度ごとに違いが生じる場合があるため、事前に案内を読みましょう。
| 出願方式 | 手続き内容 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| インターネット | 必要書類のアップロード・申請 | 期日に余裕を持って対応 |
| 郵送 | 書類の郵送・手数料支払い | 送付状況を必ず確認 |
出願時は試験会場の指定や希望の可否などの詳細も、案内ページで確認しておきましょう。
試験時間割や科目内容に関する質問
論文式試験は3日間にわたって実施され、試験科目は会計学を中心に複数分野から出題されます。代表的な科目は「会計学」「監査論」「企業法」「租税法」などです。各日の科目スケジュールや開始・終了時刻は年度で変動するため、最新発表の時間割一覧を必ずチェックしてください。
試験当日は、受験票とともに、筆記用具や認められた資料のみ持ち込めます。会場ごとに受付開始・試験開始時間が異なることもあるため、予め確認しておくと安心です。有効な学習方法としては、過去問演習や直前対策講座の活用が多くの受験者から支持されています。
主な論文式試験の科目一覧(例)
| 試験日 | 午前科目(例) | 午後科目(例) |
|---|---|---|
| 1日目 | 会計学 | 監査論 |
| 2日目 | 企業法 | 租税法 |
| 3日目 | 経営学・選択科目 | 追加選択科目 |
短答式試験との関係や科目免除についても、公式発表で逐一確認しましょう。
合格発表や次のステップに関する質問
論文式試験の合格発表は、例年11月から12月ごろに公表されることが多いです。合格者発表の日時や方法は、会計士審査会などが公式ウェブサイトやマイページにて案内します。合格発表日にはアクセスが集中するため、事前に受験番号などを準備しておくとスムーズに確認できます。
合格後は、各種登録申請や実務補習の案内が届きます。実務経験を積むことで、公認会計士として登録できる流れとなります。合格後もスケジュール管理が重要となるため、公式からの案内通知や次のステップの締切にも注意が必要です。不明点があれば、公認会計士協会や試験事務局へ問い合わせましょう。
合格発表日の主なポイント
-
発表はマイページまたは公式ウェブで案内される
-
合格証書の受け取り方法は案内どおり早めに手続きする
-
合格者名簿への記載についても確認が必要
しっかりした事前準備と最新情報の確認が、合格への近道となります。