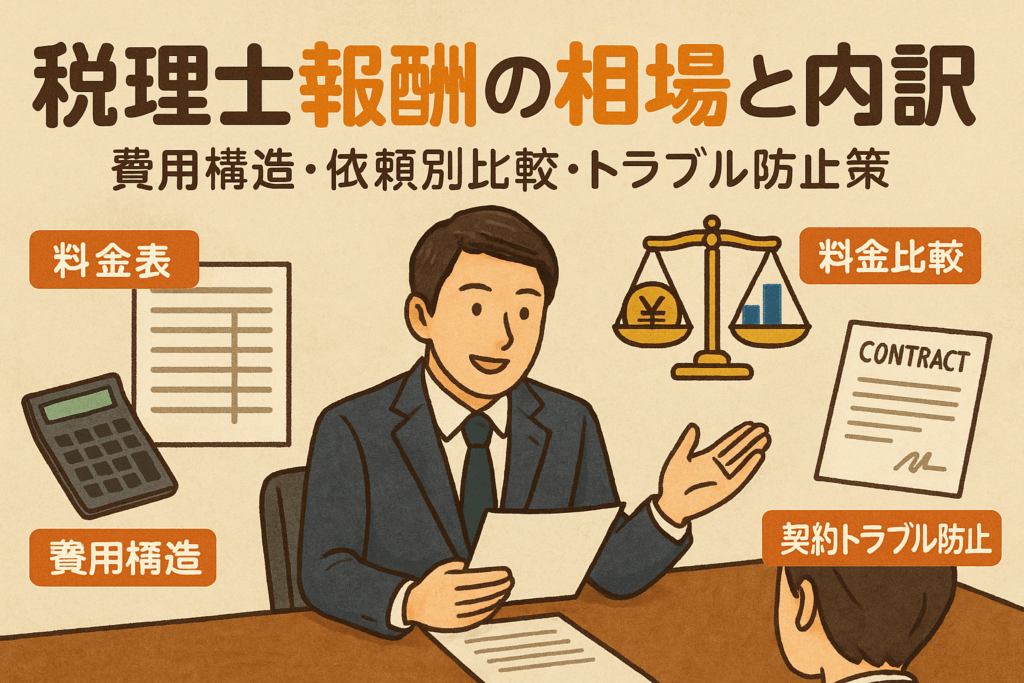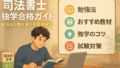「税理士報酬って、いくらが妥当なの?」――そう感じたことはありませんか。実際に【中小企業庁】の調査では、税理士費用が経営コストの中で大きな割合を占めるケースが多く、法人の場合の平均月額顧問料は約【3〜5万円】、決算申告料は【10〜30万円】と幅広いことが明らかになっています。
個人事業主なら確定申告料が【2万円〜8万円】、一方で相続税申告では【20万円〜100万円超】と、依頼内容や契約形態によって必要な金額や内訳が大きく異なるのが現実です。「業務内容や依頼内容によって、こんなに違うの?」「契約後に思わぬ費用を請求されたらどうしよう…」と心配になる方が多いのも頷けます。
さらに現在は【自由化以降】、報酬基準が廃止され各事務所ごとの価格差やオプション変動も大きく、ネットで検索しても「何を基準に選べばいいのかわからない」と感じている方も多いでしょう。
このページでは、税理士報酬の基本から最新相場、契約別の詳細な費用構成、市場変化のポイント、失敗しない比較方法まで徹底的に解説します。最後まで読むことで、ご自身のニーズにあった理想的な税理士選びと、賢い費用の抑え方が分かります。
「損をしないために知っておきたい」実例や具体的な数字も交えて紹介しますので、どうぞじっくりご覧ください。
税理士報酬についての基礎知識と全体像の理解
税理士報酬とは何か?費用の範囲と報酬規定の変更経緯を詳述
税理士報酬とは、税理士に税務相談や申告書の作成、会計処理などを依頼した際に発生する費用の総称です。顧問契約、決算申告、記帳代行、相続税申告など、業務内容ごとに報酬が設定されており、取引金額や事業規模によって金額が異なります。
以前は全国共通の料金表(報酬規定)が存在し、税理士報酬にも明確な基準がありました。しかし2002年の規定廃止により、現在は事務所ごとに自由に料金を設定できる仕組みとなっています。そのため、サービスや地域、依頼内容によって金額が大きく変動することも特徴です。
税理士報酬には消費税が加算され、法人・個人を問わず支払いが必要です。報酬には源泉徴収の義務が生じる場合もあり、会計上は「税理士報酬」や「支払手数料」などの適切な勘定科目に計上します。
税理士報酬の最新相場と料金体系の具体例
税理士報酬の料金体系は多岐にわたり、依頼する業務ごとに相場が異なります。代表的な業務別の料金目安を一覧表にまとめました。
| 業務内容 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 月額顧問料 | 0.5〜3万円 | 1〜5万円 |
| 年間決算・申告料 | 3〜10万円 | 10〜30万円 |
| 記帳代行料 | 0.5〜2万円 | 1〜3万円 |
| 確定申告 | 3〜15万円 | — |
| 相続税申告 | 30〜100万円超 | — |
主な特徴は以下の通りです。
- 依頼内容や件数、資料のまとまり具合によって報酬が増減する
- 相続税や贈与税申告は遺産総額をもとに加算方式が多い
- 法人の顧問契約は月額報酬+年1回の決算料が基本
- 消費税や源泉徴収の扱いにも注意が必要
複数の税理士事務所から見積もりを取り、料金表や内訳、オプション内容を確認することが失敗しないコツです。
過去から現在までの税理士報酬の自由化と市場変化
かつて税理士報酬は旧税理士報酬規程に基づき、全国統一の料金が決まっていました。このため利用者も明確な目安で依頼可能でしたが、2002年に規程が廃止されてからは完全な自由化となりました。廃止の背景には、市場競争の促進とサービスの多様化、利用者の選択肢拡大を目指す行政の方針があります。
自由化以降は、ネットを通じて税理士事務所の比較がしやすくなり、安価な価格帯や業種特化サービスが増加しました。報酬の高い低いだけでなく、対応内容やサポート体制、節税対策の提案力なども比較検討される時代になっています。
現代では、税理士報酬の情報公開が進み、詳細な料金表やシミュレーションツールをホームページで確認できる事務所が増えています。こうした背景から、費用だけでなく、サービス品質とコストパフォーマンスの両方を納得して選ぶ傾向が強まっています。
税理士報酬の内訳と契約別の費用構造を解剖
税理士報酬は業務内容や契約形態によって大きく異なります。しっかりと内訳や相場を把握することで、費用対効果を最大化しながら最適な依頼先を選ぶことが重要です。次のセクションでは、業務ごとの内訳や個人・法人・相続税など目的別の違い、多様な契約スタイルの特徴と報酬体系を詳しく解説します。
顧問料・決算申告料・確定申告料・相談料の詳細内訳
税理士報酬の代表的業務ごとの内訳は以下の通りです。
| 業務内容 | 主な相場 | 費用に含まれる主なサービス |
|---|---|---|
| 顧問料 | 月5,000円~50,000円 | 会計・税務相談、記帳指導、定期訪問 |
| 決算申告料 | 50,000円~300,000円 | 決算書作成、法人税申告、税務調整 |
| 確定申告料 | 30,000円~150,000円 | 個人事業主・年金受給者の所得税申告 |
| 相談料(スポット) | 5,000円~30,000円/回 | 事前相談、税務アドバイス |
注意点
- 消費税は別途加算されるケースが多く、価格表記に含まれていない場合もあるため、確認が必須です。
- 顧問契約の場合、月額顧問料に決算申告料が含まれていないことが一般的です。
個人事業主、法人、相続税、贈与税など依頼目的別費用比較
依頼する目的によって報酬体系と相場は変動します。代表的なケースを比較します。
| 依頼目的 | 主な相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| 個人事業主 | 顧問料月5,000円~30,000円確定申告料30,000円~100,000円 | 売上規模や事業内容により変動 |
| 法人 | 顧問料月10,000円~50,000円決算申告料50,000円~300,000円 | 規模・取引数・従業員数などで大きく異なる |
| 相続税申告 | 200,000円~1,000,000円超 | 遺産総額に応じて段階式で加算、加算項目も発生 |
| 贈与税申告 | 30,000円~150,000円 | 財産評価や申告書作成の難易度によって金額変動 |
ポイント
- 相続税等の特殊申告は加算項目で金額が大きくなる傾向です。
- 旧税理士報酬規程は廃止されており、各事務所が独自の料金体系を持っています。
成功報酬契約・スポット依頼・定額制など多様な契約スタイル
税理士との契約スタイルは多様化しています。代表的な契約形態と特徴を整理します。
| 契約スタイル | 概要 | 向いている依頼者 |
|---|---|---|
| 定額制(顧問契約) | 月額・年額で一定額を支払う | 定期的な税務サポートを受けたい法人・個人 |
| スポット依頼 | 必要なときだけ単発で依頼 | 単発の確定申告や相談が中心の方 |
| 成功報酬型 | 節税額や還付金など成果に応じて報酬が決まる | 相続や節税シミュレーションなど成果重視の案件 |
| 時間制契約 | 相談や作業ごとに時間単価で報酬設定 | 断続的な相談や複雑案件 |
チェックポイント
- どの契約にも源泉徴収や経費計上、契約書の確認が重要です。
- 依頼前に料金表やサービス内容を必ず確認し、不明点は事前に相談することが失敗防止のコツです。
税理士報酬が決定する要因と費用変動のメカニズム
税理士報酬は依頼者ごとの状況や要望によって大きく変動します。主な要因は企業規模、売上高、従業員数、依頼する業務の難易度、定期訪問の頻度、またオプションサービスの有無や地域性、専門分野への対応力、IT化の程度などです。正確な相場や料金表を理解することで、納得できる費用で税理士を選びやすくなります。
企業規模・売上高・従業員数による報酬の違い
税理士報酬の決定には、会社の規模や売上、従業員数が大きく影響します。売上高が高いほど経理処理の手間が増え、複雑な決算作業や各種申告対応が必要となるため、報酬も上がる傾向です。従業員数の多い企業は給与計算や社会保険対応も増えるため、顧問料や決算料の加算対象となります。具体的な料金相場の目安は以下のとおりです。
| 種類 | 小規模法人 | 中規模法人 | 大規模法人 |
|---|---|---|---|
| 月額顧問料 | 10,000~30,000円 | 30,000~70,000円 | 70,000円以上 |
| 決算料・申告料 | 50,000~150,000円 | 150,000~400,000円 | 400,000円以上 |
| 従業員数(目安) | 1~10人 | 11~50人 | 51人以上 |
企業の規模ごとで業務量・作業ボリュームが異なるため、料金が変動する点に注意が必要です。
業務内容の難易度・訪問頻度・オプションサービスが報酬に与える影響
税理士への依頼は、記帳代行や経理・税務申告から経営コンサルティングや節税アドバイスまでさまざまです。業務が複雑になればなるほど、作業工数や必要な知識レベルが高くなるため費用は上昇します。訪問頻度も、毎月訪問・四半期ごと・年数回などにより料金が異なり、訪問回数が多いほど高額になる傾向です。
また、以下のようなオプションサービスも追加料金の対象です。
- 相続税申告
- 贈与税や譲渡所得対応
- 資金調達サポート
- 税務調査立会い
- IT会計ソフトの導入支援
これらを組み合わせることで、見積もり金額が大きく変動するため、依頼前には希望内容を明確に伝えることが重要です。
地域差・専門性・IT導入状況に伴う価格差
税理士報酬は、事務所の所在地や地域性、担当税理士の専門性や経験値によっても変動します。都市部は賃料や人件費が高いため、報酬相場もやや高めとなる傾向です。一方で、専門特化型や複雑な税務案件・相続税業務を得意とする税理士は、専門知識やノウハウを含むため価格が上乗せされる場合があります。
IT導入やクラウド会計など新しいツールを積極活用する事務所は、効率化されている分、リーズナブルな価格で対応していることもあります。依頼先の事務所ごとの特徴やサービス内容を比較検討することが、納得できる税理士選びに繋がります。
| 比較項目 | 地方エリア相場 | 都市部相場 | IT活用事務所 |
|---|---|---|---|
| 顧問料 | 8,000~25,000円 | 12,000~40,000円 | 10,000~30,000円 |
| サービス提供の特徴 | 地域密着・小規模対応 | 幅広い業種・複雑案件可 | 業務の効率化、迅速対応 |
税理士報酬の税務処理方法と源泉徴収の実務
会計上の勘定科目分類と経費計上の具体的手順
税理士報酬は企業経営や個人事業において必要不可欠な経費となります。会計処理では「支払報酬」「支払手数料」「専門家報酬」などの勘定科目で仕訳します。法人の場合、税務申告や会計監査などで発生する報酬も同様の科目に計上しますが、経費区分の正確な判断が損金算入可否に直結するため厳密な分類が必要です。
具体的な計上手順は以下の通りです。
- 契約内容や報酬明細を確認
- 適切な勘定科目を選定
- 支払時の請求書・領収書を保存
- 月次・年次決算で忘れずに費用計上
中小法人では、税理士への月額顧問料や決算料、個人事業主の場合は確定申告や記帳代行料など、それぞれ該当するサービスごとに勘定科目の設定がポイントとなります。
| 依頼内容 | 勘定科目例 | 経費区分 |
|---|---|---|
| 顧問料 | 支払報酬、手数料 | 販売費・一般管理費 |
| 決算業務 | 支払報酬、決算費用 | 販売費・一般管理費 |
| 相続税申告 | 支払報酬、相続関連費 | 特別損失(個人) |
適正な分類と証憑書類の整理が、後の税務調査対応や節税面でも重要な役割を果たします。
税理士報酬に対する源泉徴収の計算方法と対応策
税理士報酬を支払う際には、一定金額以上の場合必ず源泉徴収が必要です。個人税理士への支払い時は10.21%(復興特別所得税を含む)を差し引いて支払います。計算の基準となるのは消費税を除いた報酬額です。
源泉徴収の実際の流れ
- 税抜金額に10.21%を掛ける
- 源泉所得税控除後の金額を税理士へ振込
- 翌月10日までに税務署へ納付
例:税抜10万円(消費税1万円)の場合
10万円 × 10.21% = 10,210円(源泉徴収額)
振込額は100,000+10,000-10,210=99,790円
| 報酬額(税抜) | 消費税 | 源泉徴収額 | 支払額(実際の振込) |
|---|---|---|---|
| 100,000円 | 10,000円 | 10,210円 | 99,790円 |
| 300,000円 | 30,000円 | 30,630円 | 299,370円 |
なお、税理士法人へ支払う場合は原則として源泉徴収は不要です。間違って源泉徴収をしないまま支払ってしまった場合は、速やかな修正申告対応が求められます。
消費税など税理処理における留意点と正確な申告のポイント
税理士報酬には原則として消費税が課税されます。請求書上で消費税額が明示されている場合、仕入税額控除が可能となりますので、経費処理の際には消費税区分も正確に管理が必要です。
主な留意点をリストアップします。
- 税理士報酬には課税取引と非課税取引があるため、業務内容ごとの分類が重要
- インボイス制度にも対応できる請求書の保存が求められる
- 決算・確定申告時には報酬支払いと源泉徴収、消費税区分の突合作業が必須
- 相続税や贈与税など専門報酬の勘定科目や会計処理にも注意
誤った税務処理や源泉徴収漏れは、後日の調査でペナルティ対象となる可能性があるため、適切な手順と正確な会計記録が大切です。専門家のアドバイスを受けることで、安心して経費計上や税務対応ができる環境づくりを図ることができます。
代表的な依頼ケースにおける税理士報酬の具体的実例紹介
確定申告の報酬相場と依頼時の費用構造
個人事業主やフリーランスが税理士へ確定申告を依頼する際の報酬は、収入規模や業務内容によって変動します。目安としては、シンプルな所得税申告で3万円から15万円程度が相場です。年金生活者や副業所得のみの場合、さらに低額となるケースもあります。確定申告業務では、記帳代行料やレシート整理料、書類作成の有無によって加算されることがあります。以下の表は主要な費用構造を整理したものです。
| 業務項目 | 相場目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 確定申告書作成基本料 | 3万円~15万円 | 事業規模で変動 |
| 記帳代行 | 5千円~2万円/月 | 領収書数に応じて変動 |
| 丸投げプラン | 10万円~20万円 | 全作業委託の場合 |
| 消費税申告 | 2万円~5万円 | 課税事業者の場合 |
特に個人事業主の場合は、売上規模や業種、提出書類のボリュームによって科目設定やオプションが選択されるため、事前の見積もり取得が重要です。
相続税申告・贈与税申告の料金体系と相場比較
相続税申告では、遺産総額や相続人の数、不動産や株式の評価の複雑さに応じて報酬が決定されます。一般的な相続税申告の料金体系は「遺産総額×報酬率+加算項目」の形を取るのが主流です。目安は100万円から200万円前後が多いですが、遺産総額が少ない場合や簡易申告のみなど条件によって変動します。贈与税申告も30,000円から100,000円程度の相場があります。
| 項目 | 基本報酬例 | 加算項目 |
|---|---|---|
| 相続税申告 | 30万円~100万円程度 | 財産評価や株式、不動産等 |
| 贈与税申告 | 3万円~10万円程度 | 高額贈与や特例適用 |
| 報酬率例 | 0.5%~1.0%(遺産総額) | 相続人追加ごと加算 |
財産内容や対応範囲によって報酬が増減しますので、個別ケースごとに詳細な見積もり確認が不可欠です。また、源泉徴収や各種経費精算に関しても確認が必要です。
年末調整・税務調査・法人設立など特殊業務における費用実例
年末調整や税務調査立会い、法人設立サポートなどの特殊な業務依頼の場合も料金が発生します。年末調整は従業員数や作業量によって、1人あたり1,000円~3,000円、また書類作成一式で2万円~5万円程度です。税務調査の立会いでは1日あたり5万円~10万円程度、法人設立サポート料は5万円~20万円前後が目安です。
| 業務分野 | 報酬相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 年末調整 | 1,000~3,000円/人 | 最低報酬あり・規模で変動 |
| 税務調査立会い | 5万円~10万円/日 | 事前打合せ料別途あり |
| 法人設立 | 5万円~20万円 | 登記費用等は別途必要 |
特殊業務を依頼する際は、報酬以外に必要な経費や追加料金の有無もあらかじめ確認しておくことが大切です。税理士報酬は業務ごとの課金体系が多いため、自社や個人の状況に最適なプランの選択がポイントとなります。
税理士報酬の見積もり比較と費用最適化の実践ガイド
複数税理士の報酬比較に役立つ料金比較表の作成と閲覧法
税理士報酬を比較する際は、各事務所の料金表や費用相場を正確に把握することが重要です。主な項目としては顧問料、決算料、確定申告料、相続税申告料などがあり、それぞれに標準相場や料金幅が存在します。下記に一般的な料金相場を一覧形式で整理しました。
| サービス内容 | 個人事業主の相場 | 法人の相場 | 相続税申告の相場 |
|---|---|---|---|
| 顧問料(毎月) | 5,000円~3万円 | 1万円~5万円 | ― |
| 決算・申告料 | 3万円~10万円 | 10万円~30万円 | ― |
| 相続税申告報酬 | ― | ― | 20万円~70万円以上 |
| 記帳代行料 | 5,000円~2万円 | 1万円~2万円 | ― |
確認ポイント
- 必要な業務内容が追加料金となる場合があるため、見積もり取得の際は「オプションの有無」「消費税・源泉の取り扱い」などを確認すると安心です。
見積もり依頼時のチェックポイントと質問例を具体的に提示
税理士に見積もりを依頼する際は、金額の内訳や計算根拠、今後の契約条件まで詳細に確認することでトラブルを回避できます。特に以下の点は事前に必ず確認しましょう。
- どの業務が報酬に含まれているか
- オプション業務や不定期対応の追加費用
- 源泉徴収や消費税の適用有無
- 見積書の有効期限や契約期間
見積もり依頼時の質問例
- 顧問料や相続税申告報酬の具体的な金額とその内訳を教えてください
- 決算料・記帳代行料など、追加で発生する可能性のある費用をすべて提示してください
- 業務内容に変更が生じた場合の費用はどのようになりますか
- 報酬の源泉徴収や消費税の取り扱いについて教えてください
このような項目を丁寧に確認することで、見積もりの透明性が高まり、最終的な契約後の安心にもつながります。
税理士報酬の費用を抑える具体的節約術と交渉テクニック
税理士報酬を抑えるには、無駄なサービスのカットや必要な業務のみ依頼することが有効です。さらに、複数事務所で見積もりを取り、根拠をもって交渉することで割安な提案を受けられる場合もあります。
節約ポイント
- 契約する業務範囲を明確にし、不要なオプションを削減する
- 自社で対応できる作業(記帳・資料整理など)は自分で行う
- 料金表や相場を複数入手し、比較材料とする
- オンライン面談など、訪問回数削減で費用を抑制可能か相談する
おすすめの交渉テクニック
- 相見積もりを取得し、その内容をもとに値下げ交渉を行う
- 他社よりも専門性や対応力の高い事務所にはポイントを伝えて質の担保と両立を目指す
これらのポイントを押さえることで、信頼できる税理士との適正価格での契約が可能となります。費用の透明性も高まり、無駄な支出を回避できます。
税理士契約での報酬トラブルの防止策と事前対策
報酬設定でよくあるトラブル事例の分析と未然防止策
税理士報酬に関するトラブルは、設定の不明確さや追加料金の認識違いから発生しやすい傾向があります。特に税理士報酬の相場や具体的な料金表を提示せずに契約を進めると、後々「思ったより高額だった」「料金体系が分かりにくい」といった問題が起こりやすくなります。
以下の未然防止策が重要です。
- 必ずサービスごとの税理士報酬の料金表を提示してもらう
- 追加作業やオプション料金が明記されているかを確認
- 税理士報酬規定の有無・範囲を事前説明でチェック
- 消費税や源泉徴収の扱いも最初に確認
- 業務範囲や進行中の作業量変更時の費用変動条件を明確にしておく
上記などの対応で、契約段階から不安や誤解を防ぐことが可能となります。
信頼できる税理士を見極める条件と選定基準の明確化
信頼できる税理士事務所を選ぶには、料金の安さだけでなく透明性や説明責任が徹底されているかの確認が不可欠です。また、税理士報酬規程が整備されているか、適切な報酬明細を出しているかも評価ポイントとなります。
選定時は、以下の点に注意しましょう。
| 選定基準 | チェックポイント |
|---|---|
| 税理士報酬の透明性 | 料金表や業務内容を明示するか |
| 説明責任 | 契約前の説明が丁寧か |
| 業歴・実績 | 似た規模や業種への対応経験があるか |
| 契約内容 | 書面化・明細化されているか |
| コミュニケーション | 質問への対応が迅速・誠実か |
これらの条件を比較の軸として持つことで、安心して長期的なパートナーシップを築ける税理士選びができます。
契約書や報酬明細などの書面管理で押さえるべき必須項目
税理士との契約では、口頭だけのやりとりに頼らず、書面で報酬内容や業務範囲を記録することが報酬トラブル防止につながります。
契約書や報酬明細では以下を明示しましょう。
- 契約期間および更新条件
- 業務内容(顧問、決算料、申告報酬等)
- それぞれの料金・報酬相場・料金表
- 消費税・源泉徴収の記載有無
- 報酬の支払い時期
- 追加費用や作業量変更時の取り決め
これらを書面管理することで、トラブル時の対処や費用見直しもスムーズに行えます。特に相続税や確定申告、決算などイレギュラーな業務の場合は細かい明細管理が重要となります。
普段から書類の保存と確認を徹底し、安心して税理士契約が続けられる体制を整えておくことが大切です。
よくある質問を織り込んだ実用的な相談Q&A集
税理士報酬の算定方法に関するQ&A
税理士報酬の算定方法は、業務内容や取引量、会社や個人の規模、依頼頻度などによって異なります。主な項目には顧問料、決算料、確定申告料、記帳代行料などがあり、売上や資産規模、作業量で金額が変動します。また、かつて存在した「税理士報酬規程」は廃止されていますが、多くの税理士事務所が旧規定や業界相場を参考に設定しています。下記の表は、おおよその料金イメージです。
| 業務内容 | 個人相場(円) | 法人相場(円) |
|---|---|---|
| 顧問料(月額) | 5,000~30,000 | 10,000~50,000 |
| 決算・申告料 | 30,000~150,000 | 50,000~350,000 |
| 相続税申告 | 200,000~1,000,000 | 300,000~1,500,000 |
| 贈与税申告 | 30,000~200,000 | 50,000~250,000 |
頻度や依頼範囲、オプションで料金は大きく上下するため、見積もり時には詳細な希望を伝えることが重要です。
個人・法人の依頼費用に関する疑問解消
個人と法人では、依頼する業務や事業規模に応じて税理士報酬の相場が異なります。個人の場合は確定申告の代行依頼が中心ですが、法人の場合は月次処理や経営サポートなど継続的な顧問契約が基本となります。下記の比較リストを参考にしてください。
- 個人:主に確定申告代行や記帳のみの依頼が多い。相続税や贈与税申告は特別料金になるケースがある。
- 法人:月々の顧問契約を土台に、決算業務・節税対策・資金調達の相談など多様なサポート料金が加算されやすい。
- 年間費用は個人事業主で10~30万円、法人で20~100万円規模となることが一般的です。
適正な費用かどうかはサービス内容やサポート範囲をよく確認し、複数の税理士から見積もりを取るのがポイントです。
源泉徴収や税務処理に関する実務的質問回答
税理士報酬を支払う際、多くの場合で源泉徴収が必要になります。個人の税理士や税理士法人に支払う報酬のうち契約内容によって、現行では10.21%を源泉徴収し納付する形式です。会計処理では勘定科目として「支払手数料」や「税理士報酬」を用いるのが一般的。源泉徴収をしない場合は納付漏れとなり、ペナルティの対象となることもあるため注意が必要です。
源泉徴収の計算式
支払額 × 10.21%=源泉税額
(例:税理士報酬10万円の場合 → 10万円 × 10.21%=10,210円)
報酬の領収証や納付書作成も忘れずに行いましょう。
見積もりや契約に関する交渉・トラブル疑問のクリア
税理士報酬の見積もりを依頼する際は、業務範囲・訪問頻度・オプション費用・消費税の有無など明細を明確にしましょう。契約書は必ず締結し、不明点は遠慮なく質問を。
よくあるトラブル例と、事前に防ぐポイントをリスト化します。
- 想定外の追加費用が請求された
- 報酬の内訳が不透明で説明がなかった
- 契約範囲外の対応を求められた
これらを避けるためにも、料金表や契約条件、解除ルールなどをしっかり確認しましょう。
特殊ケース(相続・贈与・税務調査など)における費用質問への回答
相続税申告や贈与税申告は一般的な業務よりも高額になる傾向があります。相続の場合、遺産総額や相続人の数、不動産や株式の有無などで大きく異なります。
また、追加で税務調査対応や遺産分割協議書の作成を依頼する場合は、加算料金が発生します。依頼時には「何にいくらかかるのか」を明記した詳しい見積もりを必ず取りましょう。
| 項目 | 報酬目安 |
|---|---|
| 相続税申告基本料 | 30万円~100万円 |
| 贈与税申告 | 3万円~20万円 |
| 税務調査立会料 | 5万円~20万円 |
税理士選びで迷ったら、実績や説明の分かりやすさ、アフターサポートの有無に注目すると安心です。